134 / 150
第七部 第二章 ファイナル・ランウェイ
第七部 無色透明(クリアカラー)の喜び 第二章 1
しおりを挟む第二章 ファイナル・ランウェイ
* 1 *
ひと山いくらで売っていそうな金属製の事務机と、その机には不釣り合いなほど高級なオフィスチェアが置かれた決して広いとは言えない部屋の主は、ニッカと人好きのする笑みを浮かべている。
髪が頭頂部を守ることがなくなったために、ただでさえ丸かった顔がまん丸に見える初老の域に達している男性は、しかしスラックスを穿き作業用のブルゾンを羽織る身体は服の上からでもガッシリとしているのが覗え、その年代によくある腹の出っ張りも見られない。
「どういったご用件で?」
ピクシードールのものかと思うくらい大きく、節くれ立った古傷だらけの手を机の着いて笑みを投げかけてきている彼に、音山彰次は若干緊張しつつもいつも通り素っ気ない口調で問うた。
「まぁそんなに焦るな。ほれ」
机の上に置かれていた缶コーヒーの一本を投げ渡してきて、気さくな口調で言う彼は、HPT社の社長。
日本では第二位、世界でも十位以内に入るスフィアドール業界の重鎮と言える企業となった、ヒューマニティパートナーテックの社長であり、創業者。
応接室も作業室も別にあり、社長室とは名ばかりの引きこもり部屋は、HPT社が町工場だった頃の社長室を再現したような簡素な造作となっている。その方が落ち着くのだそうだ。
プルタブを開けて缶コーヒーを一気に飲み干し、意外に乾いていた喉を潤した彰次は、社長の言葉を待つ。
「まぁなんだ、今後の話を少ししておこうかと思ってな」
「今後の話、ですか」
ニコニコと笑っている社長の真意は、その言葉と表情からは読み取れない。
突然のスフィア一斉機能停止から間もなく二週間、機能回復を諦める空気が流れ始め、事実上の市場消滅後については、会議でも会議外でも幾度も話題に上がっているし、決定は出ていないが方針も固まりつつある。
社長が彰次を呼び出して話したいのは、スフィアドール業界の今後についてかもしれないが、その話だけでは済まないだろうことは推測できた。
「基本、貴方の方針に従いますよ。拾われた身ですからね、俺は」
「あれだけ好き勝手やっておいて、よく言うな」
「それも含めて、貴方の方針だったじゃないですか」
「それはそうなんだがな」
苦々しげに、しかし嬉しそうに笑む社長は、そう応えて禿げ上がった頭を撫でた。
東雲映奈を失った後、惰性で大学院に進んだ彰次だったが、未来を見ることができず、就職先も決めずに腐っていた。
そんな折り、偶然会社説明会で出会った社長は、彰次のことを拾ってくれた。何かを見出したのか、気まぐれだったのかはよくわからない。
口数も少なく、態度も悪かった当時の彰次を、卒業したら会社に来いと言ってくれたのは、彼だけだった。
入社当時、製造工場用アームロボットの部品をつくっている町工場だったHPT社は、一大決心と言える方針転換でスフィアドール市場に参入し、いまでは業界の中では日本だけでなく世界でも知らない人はいないほどの会社となっている。
自ら腕を振るっていたしがない技術屋だった社長が、そこまで会社を育ててきた結果だ。
そんな社長に、彰次は返しきれないほどの恩を感じている。
「さて、要件だが」
自分も缶コーヒーを飲み干した社長が、おもむろに言った。
「来年度早々、うちから部門を分割して、名前はまだ仮だが、クリーブテクノロジーを設立する」
「ずいぶん話が早いですね。まぁ、いまの状況ならば仕方がないですが」
克樹からは簡単なものだったが、スフィアの機能停止などについて連絡が来ていた。
リーリエのこと、百合乃のことはすぐにでも話を聞きに行きたかったが、ここ何日もまともに家に帰れていないほど忙しい状況だ。
スフィアの機能復活が諦められつつあるいま、性能は不十分でもスフィアの代わりとしてクリーブが注目されるのは当然のこと。大きな事業になることを見越して部門を会社として独立させるのもよくある動きで、確かに早いと感じる決定ではあったが、不思議に思うほどではない。
――いや、平泉夫人が手を回しているな。
クリーブにかなりの金額を投資したり、発表を急がせたりと、すべてを見透かしていたようにも思える平泉夫人が、クリーブテクノロジーの設立にも深く関わっているだろうと、彰次は読み取っていた。
「お前の、ではあるが、表向きはうちから出てきた技術と製品だから、うちが筆頭株主にはなるが、クリーブテクノロジーはスフィアドール業界の大手のほとんどが出資する形で設立される。まずは間借りの工場を使うことになるんだけどな、早々に大型工場を国内に建設する予定だ」
「ほんの数日の間に、ずいぶん話が大きくなりましたね」
「まぁな。――で、お前にはそこの社長をやってもらうから」
「……」
なんでもないことのように言う社長に、彰次は頭が真っ白になる。
参加企業の名前や出資金額などの具体的なところがわからないから把握しきれないが、業界関係会社が寄ってたかって設立する会社だ、HPT社の子会社なんて規模でないことは確実だった。
そんなところの社長に抜擢すると、それも世間話のように言われれば、言葉も出てこなくなる。
「どうした?」
「いや……、いきなりだったので」
「確かにいきなりだが、お前しかいないだろう? クリーブを発明したのはお前だ。その会社をつくるなら、お前以外に社長になれる奴はいない」
「それは……、そうかも知れませんが……」
彰次は顔を歪めて不満と困惑を表すが、社長は気にした様子もなく口元に笑みを貼りつかせている。
クリーブの発明は確かに彰次の発想を元にしているし、会社はその特許を彰次名義で取らせてくれている。
しかし開発には会社の設備を使っていたし、いま現在急ピッチに進めている性能向上の試みは、すでに彰次の手を半ば離れ、若手が中心メンバーとなって進めている。
自分だけのものという意識が、彰次には薄かった。
「今後、スフィアドールと呼ばれていたロボットは、クリーブドールと呼ばれるようになる。お前はオレなんて超えて、業界のトップに君臨することになるんだよ」
「それはむしろ、面倒臭いですね」
いまの状況からすると、近い将来起こり得るだろうことを言われて、彰次は鼻にシワを寄せた。
つい先月まではいつ開発中止になるかとささやかれ、彰次自身もそれを思っていたクリーブ。
それがたったひと晩の間に起こった出来事で、えらい変わり様だ。
――平泉夫人の反撃だな。
モルガーナに受けた攻撃を生き残った平泉夫人による、何倍返しにもなる反撃。
彰次はそれに巻き込まれたことを意識した。
――社長なんてまっぴらゴメンなんですがね。
無駄だろうと思いながらも、机に片手を着いて身を乗り出した彰次は社長に言葉を返す。
「俺は技術開発部長っていまの立場が一番性に合ってるんですよ。クリーブテクノロジーに籍を移して、クリーブの開発をするのも構わない。ですが、俺は現場が一番やりたいことができる人間です」
「お前のことだからそう言うとは思ったがな。だが、社長って立場も悪くはないぞ?」
そう言った社長は、唇の端をひん曲げるようにして笑う。
技術屋だった社長は、自らレンチやヤスリを持って現場で作業していたような人物。
現在では現場には顔を見せる程度になってしまっているが、そうなったのは社長業が忙しくなったからなどではなく、長年の無理が祟って腱鞘炎を患い、現場作業が難しくなったことが大きい。
HPT社をここまで育て上げた経営手腕も疑いようはないが、彰次にとって社長は現場の人という認識の方がいまだに強い。
彰次もまた現場人間であるというのは、社長も共通して持っている認識だと思っていた。
「社長ってなぁ会社ってものを使って、世の中を動かしていく仕事だ。足下もちゃんと見てねぇと武器になるはずの会社が足かせになったりもするし、直接相手をする取引企業や個人はともかく、業界ってなぁ雲よりもつかみどころがない上に、妖怪変化の類いがそこら中にいやがる」
「言い得て妙なことを」
部長職にある彰次は、現場の仕事だけでなく対外的な仕事も多くこなしている。
業界という形があるようではっきりしないものに対する感想は、社長がいま言った言葉に全面的に同意できた。
「だが会社を使って業界を、世界を切り開いていける。関われるのはほんの一端に過ぎないが、嫌いな流れを潰したり、望みの世界を生み出していく、夢を世界に実現していく仕事だ。現場の仕事が楽しいのはわかるし、あんまり身勝手なことやってると自分が潰されちまうが、見方を変えれば面白いぞ」
「……」
腱鞘炎が悪化し、現場を離れなければならなくなった時期、社長がふさぎ込みがちだったのは、彰次もその目で見て知っている。その後スフィアドール業界に邁進していくようになった彼は、そうやって考え方と気持ちを切り換えていったのだろう。
どこか凄みと深みのある笑みを浮かべている社長に、彰次は改めて尊敬の念を抱いていた。
尊敬している社長の言葉でも乗り気にならない彰次は、もう飲み干しているコーヒーの缶を仰いでわずかな滴で舌を潤す。
「それとよ、お前の相方になる人物は社長なんてのよりもうひとつ広い世界で生きてく人間になるんだろ? 肩を並べるまでは行かなくても、支えられる立場にならなくてどうするよ?」
「ぐっ……」
缶を放り出す勢いで机に置いて、彰次はむせそうになった口を押さえる。
自分と芳野の関係については、言わずともひと目でバレてしまった平泉夫人以外には、誰にも話したことはない。
「な……、なんでそんなことを……」
「ちょいと前のお前の動向、オレが把握してないと思ってんのか? 平泉夫人が入院してからは、忙しいとき以外は仕事を持って帰らねぇお前が積極的に在宅作業に切り換えてたしよ。仕事中もどっか上の空だったし、個人のことにゃああんまり突っ込む気はなかったが、噂になってたからな。いくらなんでも行動があからさま過ぎて噂にもならぁな」
「噂に、なってたんですか……」
楽しそうに笑っている社長に、彰次は苦々しげな顔を向けることしかできなかった。
いまから思い返してみれば、平泉夫人が銃撃されて入院し、目覚めるまでは、明らかにこれまでと違う行動パターンを取っていた。具体的な内容がバレることはなくても、噂になってもおかしくないと自分でも思えるほどに。
クリーブの大口出資者ということで、彰次が平泉夫人に会いに行く機会は増えていたのでごまかせていると思っていたが、社長にはお見通しだったらしい。
「お前のお目当ては夫人の後ろにいつも立ってたお嬢さんだろ?」
「……」
「いまさら隠すことでもないだろうよ。遊んでる時間は終わって、腹を括る時が来たってだけだ」
「……まぁ、社長の言う通りなんですがね」
肯定の返事をした彰次は、項垂れて大きなため息を吐いた。
ニヤニヤとイヤな笑みを浮かべていた社長だったが、表情を引き締める。
「そのお嬢さんだが、平泉夫人の後継者になることを承諾したそうだ」
「綾……、芳野さんが?」
「あぁ。平泉夫人から連絡があった。娘というほどには歳は離れていないし、夫人も引退する予定があるわけじゃないそうだから、一緒に仕事をする形になるんだそうな。正式な発表はまた後日、関係者には連絡があるそうだよ。――んで、お前はどうする?」
年齢だけでなく、様々な経験をしてきた凄みのある視線で見つめてくる社長。
――綾も、自分を変えていくつもりなんですね。
平泉夫人が目覚めてからは、エリキシルバトルの話を聞いたときにしか会っていない芳野。
ゆっくり話をすることができなかったそのときにも、その前の平泉夫人が入院したときにも、彼女の微妙な変化には気づいていたが、その後にも大きな気持ちの変化があったらしい。
――俺も、いつまでもいまのままではいられない、か。
腹を括る時、まさにいまそれが来たことを、彰次は感じていた。
「わかりました。クリーブテクノロジーの社長の件、受けますよ」
「くっくっくっ。まぁまだ、正式な承認は下りてないし、内々の話って段階なんだがな」
「もう少し下準備をしてから話をしてくださいよ……。しかし、ずいぶん性急ですね。クリーブテクノロジーのことも、芳野さんのことも」
「まぁな。業界が激震の時期だからってのもあるだろうが、これは平泉夫人からの反撃だよ」
「反撃?」
「あぁ。魔女への、な」
「魔女……」
「お前の方が詳しいんだろ? 魔女に関しては」
これまで会社では直接言葉に出したことのない魔女の、モルガーナのことを話題に出されて、芳野のことを指摘されたとき以上に驚いた彰次は言葉を継げなくなっていた。
乗り出し気味だった身体を椅子に預け、身体ごと横を向いた社長は話し始める。
「なんで知ってるのか、なんてなぁ聞くなよ? スフィアドール業界にそれなりに籍を置いていればイヤでも気づくさ。――この市場は、何者かの意思によって操作されてる、ってな」
「それはまぁ、そうでしょうが」
「平泉夫人はいま、魔女との戦いの先頭に立ってる。オレは夫人の要請を受けて、協力することにした。これまで魔女はスフィアドール業界の発展に貢献してきたが、ここしばらくは目の上のたんこぶだった。そして、スフィアの停止だ。魔女はいま、業界から排除されるべき敵になったんだ」
「ということは、社長だけでなく、夫人の反撃には他にも参加している人がいるんですね」
「あぁ、もちろんな。そしてお前は協力者なんかじゃなく、当事者のひとりなんだろ?」
「……そうですね」
顔を振り向かせ、覗き込むように瞳を見つめてくる社長。
厳しく細められた彼の瞳からは、複雑すぎて感情を読み取りきれない。
「どんな風に関わってるかは、訊かないがな。ただ、夫人が言っていたよ。『魔女に剣を突き立てられる者は少ない』ってな」
「かも、知れませんね」
その言葉の意味するところは、だいたいわかっていた。
いま、モルガーナへの剣となれるのは、克樹だけ。
芳野と約束した、東雲映奈にまつわる過去の清算は、エイナの意思が封印されたことによってほぼ不可能となった。
そんな状況でいまさら自分に何ができるのか、彰次にはわからなかった。
――だが、次が最終決戦になるはずだ。
命懸けになるだろうモルガーナとの最終決戦。
その戦いに自分が直接関わることはできず、克樹を送り出すことしかできないことに、彰次は両の拳を握りしめていた。
「魔女退治に必要なことであれば、できるだけ協力する。多少の無茶でもどうにかして見せる。だから……、お前は死ぬなよ」
「――はい」
自分が戦場に赴くことはないだろう戦い。
社長の気遣う視線に見つめられながら、彰次は克樹たちのことを想い、唇を噛みしめた。
*
「失礼します」
芳野さんに扉を開けてもらい、踏み込んだのは平泉夫人の執務室。
夏姫と一緒に入った僕を待っていたのは、平泉夫人とショージさん、それから灯理と近藤、猛臣だった。
エイナと戦ってから二週間、一昨日平泉夫人が正式に退院したのを機に、今後の対策を練るために僕たちは集まった。
厳しい視線が僕に向けられる中、肩に背負ってきたデイパックがごそごそと動き、半開きだった口から飛び出していったもの。
「アライズ」
ふかふかの絨毯に着地する直前にそう唱えたアリシアは光に包まれ、二〇センチのピクシードールから、一二〇センチのエリキシルドールになる。
少し前に灯理からアリシア用にって贈られた、ちょっとゴスロリっぽい雰囲気のあるブラウスとジャンパースカートを身につけた百合乃は、空色のツインテールを揺らしながら膝立ちからすっくと立ち上がった。
「……久しぶり」
「うん、お久しぶりです」
緊張した空気が流れる中、最初におずおずといった感じで声をかけてきたのは、ショージさん。
ニッコリした笑みで応えた百合乃に、ショージさんと、それから平泉夫人は表情を強張らせた。
「本当に、百合乃なんだな」
「そうだよ。ショージ叔父さん。……ゴメンね」
誰にでも明け透けだったリーリエと違い、夏姫とかと話すときは口調が丁寧になる百合乃だが、僕と話すときはリーリエと同じように砕けた口調で、それから声も同じだ。
でもほんの少しだけ違う。
同じに思えるのにわずかに違う口調。
変わらないようでいて違いのある声。
それを感じるとき、僕はいま側にいるのがリーリエではなく、百合乃であることを実感する。
「本当に復活したのね、百合乃ちゃん」
「はい、平泉夫人。姿も違って、人間でもありませんが、あたしです。あたしは、音山百合乃です」
椅子に座っていた平泉夫人は、泣きそうな顔で立ち上がり、執務机の脇から部屋の中程まで歩いてくる。
下唇を噛んで堪えていた百合乃は、両腕を広げた夫人を見、煌めく滴を散らしながら走り寄り、抱きついた。
「いろいろあったようだけれど……、まずはこうしてまた貴女に会えて嬉しいわ、百合乃ちゃん」
「あたしも、です……。あたしも――」
それ以上は言葉にならず、百合乃は夫人の胸に顔を埋めて泣きじゃくり始めた。
百合乃はずっと堪えていた。
涙を流すことはあっても、再会してからずっと、大声を上げて泣くことはなかった。
平泉夫人に再会して緊張の糸が切れたのだろう。百合乃は誰にはばかることなく、声を上げて泣いていた。
百合乃が死んだのは一二歳のとき。
血縁的な意味はなくても、会って話したことはなくても、百合乃にとってリーリエは娘と言える存在。
百合乃は、自分が復活するのと同時に、娘を失った。
「リーリエが……、リーリエがっ!! あたしのために、リーリエが!」
――あぁ、そうか。
僕にとっても娘と言えるリーリエの名を呼び、泣き続ける百合乃に、僕はやっと実感する。
――僕は、リーリエを失ったんだ。
鼻をすすって涙を堪えようとする。
でもそのとき背中に触れた、暖かい手。
振り向くと、声も上げずに涙を流してる夏姫がいた。
僕はもう堪えきれず、夏姫の身体に両腕を回して彼女の肩に顔を押しつけた。
それからしばらくの間は、百合乃の泣き声と、他の全員のすすり泣きが部屋を満たしていた。
やっと涙が収まってきて、僕は顔を上げる。
まだ涙が止まらない夏姫の頭を抱き寄せ、近くに立っているもうひとりの女の子に顔を向ける。
灯理。
喪服のようなシンプルで黒いワンピースを身につける彼女は、医療用スマートギアの下に残った涙の跡を拭い、僕から視線を逸らしてうつむいた。
でも少しして顔を上げ、僕に頷いて見せてきた。
百合乃を失ったことだけでなく、いろいろ想うところがあったのだろう彼女。
前の話し合いでは姿を見せなかった灯理が、今日はここに来ている。
彼女なりに気持ちの整理がついたのかどうかはわからない。それでも現実から目を逸らさずに、ここに集まってくれていた。
「大丈夫? 灯理」
「はい。……いえ、大丈夫とは言い切れませんが、逃げてばかりはいられませんから。できる限りの協力はさせてもらいます」
「うん」
かすれ気味でも、しっかりした声で答えてくれた灯理。
僕はそんな彼女に頷きを返していた。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました
フルーツパフェ
大衆娯楽
とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。
曰く、全校生徒はパンツを履くこと。
生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?
史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。



幼なじみとセックスごっこを始めて、10年がたった。
スタジオ.T
青春
幼なじみの鞠川春姫(まりかわはるひめ)は、学校内でも屈指の美少女だ。
そんな春姫と俺は、毎週水曜日にセックスごっこをする約束をしている。
ゆるいイチャラブ、そしてエッチなラブストーリー。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

GAME CHANGER 日本帝国1945からの逆襲
俊也
歴史・時代
時は1945年3月、敗色濃厚の日本軍。
今まさに沖縄に侵攻せんとする圧倒的戦力のアメリカ陸海軍を前に、日本の指導者達は若者達による航空機の自爆攻撃…特攻 で事態を打開しようとしていた。
「バカかお前ら、本当に戦争に勝つ気があるのか!?」
その男はただの学徒兵にも関わらず、平然とそう言い放ち特攻出撃を拒否した。
当初は困惑し怒り狂う日本海軍上層部であったが…!?
姉妹作「新訳 零戦戦記」共々宜しくお願い致します。
共に
第8回歴史時代小説参加しました!

【R18】俺は変身ヒーローが好きだが、なったのは同級生の女子でした。一方の俺は悪の組織に捕らえられマッドサイエンティストにされた
瀬緋 令祖灼
SF
変身ヒーロー好きの男子高校生山田大輝は、普通の学生生活を送っていたが、気が晴れない。
この町には侵略を企む悪の組織がいて、変身ヒーローがいる。
しかし、ヒーローは自分ではなく、同級生の知っている女子、小川優子だった。
しかも、悪の組織に大輝は捕まり、人質となりレッドである優子は陵辱を受けてしまう。大輝は振り切って助けようとするが、怪人に致命傷を負わされた。
救急搬送で病院に送られ命は助かったが、病院は悪の組織のアジトの偽装。
地下にある秘密研究所で大輝は改造されてマッドサイエンティストにされてしまう。
そんな時、変身ヒーローをしている彼女、小川優子がやって来てしまった。
変身ヒーローの少女とマッドサイエンティストの少年のR18小説
実験的に画像生成AIのイラストを使っています。
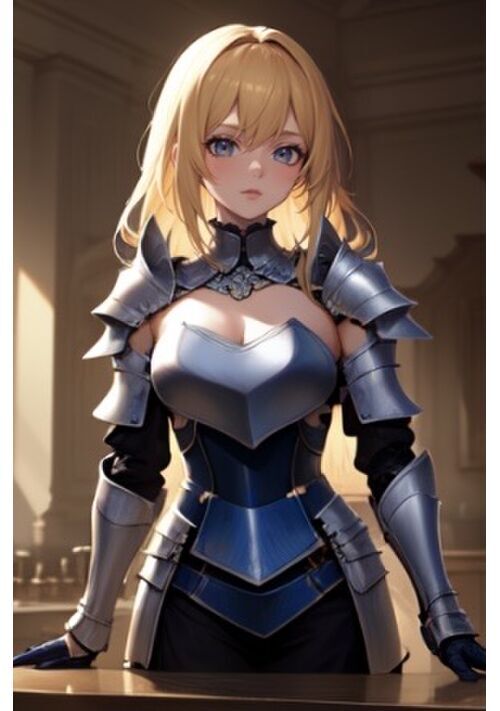
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















