128 / 150
第六部 第四章 リーリエの願い
第六部 暗黒色(ダークブラック)の嘆き 第四章 4
しおりを挟む* 4 *
見えてきた克樹の家には、明るい光があった。
「あいつ、いるのかな?」
軽いランニングを続ける赤いジャージの上下を着る明美は、そうつぶやく。
もう夜遅い時間であるのはわかっていたが、家族に気分転換のためにランニングに出てくる、と心配もされたが無理矢理家を出て来た。
もう二週間、克樹は学校に来ていない。
彼がいまどうしているのか、明美にはわからなかった。
夏姫が彼のことを知っているのは確かで、大きな病気や怪我をしてないのはわかっていたが、あまり突っ込んで聞いていなかったし、聞くことができないでいた。
ふたりの関係が、それ以前とは違ってきていることに、何となく気づいたから。
あまり詳しく聞くことを、明美はためらってしまっていた。
それでも心配は募る。
元気ならばいいけれど、夏姫も言葉を濁すばかりで、はっきりとしたことは言わない。
それに克樹や夏姫、それから近藤、さらに他に何人かが飛んでもないことに巻き込まれているらしいことには、気づいていた。
詳しいことは部外者である明美には話してくれないだろうと思っていたし、事実話してくれていなかったが、どうしても気になって、今日はとくに何か胸騒ぎがして、ランニングにかこつけて彼の家の側まで来てしまっていた。
――百合乃ちゃんのときも、克樹は酷かったもんね……。
大切な家族を、妹を失ったのだから当然だとは思うけれど、そのときの克樹はもの凄く荒れていたし、そうでないときは小さくなって消えてしまうのではないかと思うくらい沈んでいた。
酷いことも言われたし、怖い目にもあったけれど、それでも明美は克樹に立ち直ってほしくて、何度も彼の家に足を運んだ。
――でも、あのときみたいなことは、もうないよね。
夏姫が克樹の家に頻繁に出入りしてるのは知っている。
もしいま克樹が家にいるとしたら、こんな時間に訪ねて、彼女と一緒に出てこられるのは、何となく避けたかった。
ここまで来たというのに、明美はそれ以上進み出ることができなくて、曲がり角の影から、少し遠い彼の家を眺めているだけだった。
「え?」
眺めているとき、突然克樹の家の前に人影が現れた。
暗がりから現れたというのではなく、門の前に何の前触れもなく、突然姿が見えた。
バイク、にしてはずいぶんおかしな、SFアニメにでも出てきそうな一輪車の乗り物から降りた人影は、ふたつ。
ひとつは遠目にも克樹であることがわかる。
それからもうひとりは、人間とは思えない空色の髪をツインテールに結った、幼い人影。
「あれは……」
克樹を振り返り、微笑みを浮かべている小さな女の子。
「嘘っ?! そんな、まさか……」
まるでピクシードールのコスプレをしているようなその子の笑顔に、明美は驚愕の声を上げていた。
ふたりは明美に気づくことなく、門を潜って家の中に入っていった。
ブロック塀に両手を着き、震える身体を寄せて、明美はその様子を見送った。
「どうして……。どうしてあの子が、いるの?」
声が震えている。
驚きで身体から力が抜けそうになっている。
追いかけようとしたけれど、身体が動かなかった。
――でも、確かめないと。
顔を驚きに引きつらせたまま、明美はゆっくりと克樹の家に向かっていく。
気のせいかも知れない。間違いかも知れない。
そんな思いですぐには門を潜ることができず、立ち止まってしまう。
「でも、絶対そうだ」
そうつぶやいてひとつ頷いた明美は、思い切って門を静かに開け、玄関に向かっていった。
*
「うぅ……」
リーリエに肩を貸してもらってどうにか玄関に入った僕は、靴を脱ぐこともできずに玄関にへたり込んだ。
ここまで来たスレイプニールの速度は、暴走と呼ぶべきものだった。
被ったままのスマートギアで計測した結果、最高時速は二〇〇キロを超えていた。
車でその速度を出すならただ怖いで済むけど、目元はスマートギアで覆っていると言っても、もうすっかり冬のさなかにその速度となると、寒さが刺すほどに痛い。
何より車と車の間を自由に縫っていく運転は、バイクの免許すら持っていない僕にとっては、恐怖以外のなにものでもなかった。
「次からは、もう少し安全運転で頼む……」
どうにか座ることができた僕は、ぐったりとしながらも靴を脱ぐ。
「あははっ。ゴメンね。ちょっとはしゃいじゃったね」
反省の色のない無邪気な笑みを見せるリーリエは、あらかじめ用意していたらしい雑巾で足を拭き、廊下に上がった。
「克樹? 帰ってきたの?!」
「克樹さん? 大丈夫ですか?!」
「帰ってきたか……」
口々に心配の声を出してLDKから出てきた三人。
夏姫と灯理と近藤。
「――どうしてこの時間に、お前たちがいるんだよ」
「だって、心配だったから……」
「えぇ、それに大変なことがありましたし」
「あぁ。スフィアが全部、機能を停止したんだ」
「知ってる。猛臣から連絡があった」
まだ怠い身体を無理矢理奮い立たせて立ち上がった僕は、順番に三人の眺めていく。
「モルガーナがすべてのスフィアからエリクサーを抜き取って、スフィアコアの機能を停止させたんだ」
「それでは、エリキシルバトルはどうなったのですか?」
「――強制終了になった、らしい」
「そんな……」
僕の言葉に、灯理は口元を両手で覆ってしゃがみ込む。
側までやってきた夏姫は、春歌さんと話したからだろうか、意外に落ち着いていて、少しつらそうではあるけど、僕に微笑みかけてきてくれる。
「とにかく、詳しく聞きたい。中に入ろう」
眉を顰めながら言う近藤の提案に、僕はリーリエと一緒に灯理を立たせてやりながら、LDKに入る。
夏姫に暖かい飲み物を用意してもらい、ダイニングテーブルに落ち着いた。
「それで、エリキシルバトルが強制終了になったって、どういうことなのですか?」
たぶん誰よりも強く望み、そして形振り構わず願いを叶えるために頑張ってきた灯理は、深くうつむいていた顔を上げ、真っ先にそう問うてきた。
「あたしが説明した方がいいかな?」
「頼む」
「うん。えぇっと、細かいことは省くけど、魔女さんがね、サードステージのエイナさんじゃ勝てないってことで、エイナさんを無理矢理フォースステージに上げることにしたの」
リーリエからの説明が始まった。
一応スレイプニールに乗ってる間にある程度聞いていたけど、しがみつくのに必死で、半分くらいしか頭に残っていない。
「エリキシルスフィアじゃなくて、その他の普通のスフィアにもほんのわずかずつエリクサーが貯まるんだけど、そのすべてを回収しちゃったから、いまあるほとんど全部のスフィアコアは、ただの石英、水晶の球になっちゃったんだ」
「シンシアのスフィアコアは、アライズできるようにしてくれただろ? あれと同じように、機能を復活させることはできないのか?」
「できなくはないけど、いまのあたしはあんまりたいした量のエリクサーは持ってないんだ。それに、アライズはできるようになっても、エリキシルバトル自体は強制終了しちゃってるから、資格は復活しないよ?」
シンシアの機能が復活したという言葉に反応して期待を持った様子の灯理は、続く言葉で再び沈んだ表情になり、うつむいてしまった。
「スフィアドールを動かそうと思ったら機能を保持したままのスフィアに載せ替えるしかないけど、たぶん魔女さんは機能の回復なんてすることはないだろうしね」
「じゃあ……、じゃあやっぱり、ワタシの願いはもう、叶わないんですか?!」
立ち上がり、テーブルに身体を乗りだしてリーリエに詰め寄る灯理。
慌てることも、驚くこともなく、医療用スマートギア越しにも感じる鋭い視線を受け止め、静かな表情でリーリエは答える。
「うん。エリキシルバトルの参加資格があるスフィアは、あたし分と、エイナさんのしか残ってない。自分で決めたルールなのに、魔女さんが無理矢理残った人の資格を奪っちゃったからね」
「そんな……、そんなっ……。いいえ、リーリエさんに負けたワタシは、もう願いが叶わないことなど、わかっていましたが……」
力が抜けたように、ドサリと椅子に座った灯理。
リーリエと戦い、敗れた彼女。
それでも残された参加資格に、微かな希望を持っていたのはわかってる。
でもいまは、本当に、完全に資格を失ったことで、泣くこともなく、椅子の背に身体を預けて、放心したようにだらんとしてしまった。
「魔女さんが、自分の願いを叶えるために、そうしたんだよね。あの人は結局、自分の願いを叶えることしか考えてなかったから」
「それはわかるが……、お前はあのとき、どんな願いを叶えたんだ?」
訳知り顔でモルガーナのことを語るリーリエに、僕はそれを問う。
あのときリーリエは願いを叶えたはずだけど、いまだにそれがどんなものだったのかわからない。
リーリエには、何の変化も見られないんだから。
「願いを叶えたって?」
「どういうことですか? リーリエさん」
「いったい、どんな願いを叶えたんだ?」
驚いた顔の夏姫と、復活して顔を上げた灯理と、首を傾げている近藤に注目されたリーリエ。
「んーとね、魔女さんがエイナさんを無理矢理フォースステージに上げて、こっちのエリクサーを奪おうとしたんだ。だからそれに対抗するために、魔女さんの願いが叶わないようにするために、あのときはそうするしか選択肢がなかったんだよ」
「それはわかるが、お前の願いは、なんだったんだ?」
僕の問いに、悲しそうな顔になるリーリエ。
それまではしゃいでいたのとは一転して、いまにも泣きそうな表情で僕の顔を見つめてくる。
「あのとき叶った願いはね――」
「克樹?」
リーリエの言葉を遮るようにLDKの扉のところに現れたのは、遠坂。
「え? 明美? どうして?」
「なんでお前がここにいるんだよ」
「あ、いや……、えぇっと、たまたま、この近くに来てて、それで克樹たちが家に入っていくのが見えて……」
しどろもどろと言い訳がましいことを並べながら、許可もしてないのに家に入ってきて僕たちに近づいてくる彼女。
――あ、リーリエは!
明らかに人間じゃないリーリエを隠そうと、僕は立ち上がって彼女の姿が隠れるようにする。
いまさら、遅いけど。
「どいて、克樹」
「いや、これはその……、フルオートのスフィアドールで……、いまは僕の家でテストしてて……」
僕のことなんて見てなくて、後ろにいるリーリエに厳しい視線を向けている遠坂。
今度は僕が言い訳にもならない言葉を並べることになったが、遠坂の耳に入ってる様子はない。
僕の身体を無理矢理どかして、リーリエと向かい合う。
「――なんで、貴女がいるの?」
「だからこいつはエルフドールで……」
「そ、そうなんだ、遠坂」
「うん、うん。スフィアドールなんだよ、明美」
僕の言葉に同調して答えてくれる近藤と夏姫だけど、遠坂はそれを信じてくれる風もなく、僕のことを厳しい視線で睨みつけてくる。
「違う。この子は、エルフドールとか、そんなんじゃなくって――」
戦闘用のなんて造られることはないから、エルフドールはたいてい人間と同じ服を着ている。
いまのリーリエはエリキシルドールなわけで、エルフドールではまずあり得ないハードアーマーなんてのを着けてたりするけど、明美が否定しているのはそういうことじゃないようだった。
「――やっぱり、明美さんを騙すのは無理ですよね。お久しぶりです、明美さん」
椅子から立って笑むリーリエは、突然そんな、意味のわからないことを言い始めた。
「なんか……、事情はよくわからないし、その格好も訳わからないけど……。うん、久しぶり」
なんでかふたりの間だけで通じていて、そう挨拶を交わしてるリーリエと遠坂。
――そんなこと、あり得ない。
リーリエが稼働を開始した後も遠坂の奴が家に来たことはあるけど、ひと言も話さないように指示していたし、実際話したこともない。
ボディとなってるアリシアについては、けっこうデザインは変わったけど、基本のところは同じだから、百合乃が生きてる時代に見せたことはある。
でもその挨拶は不可解で、僕には状況が理解できなかった。
「気づいてないの? 克樹」
「何にだよ」
小首を傾げてる僕に、睨みつけるような視線を向けてくる遠坂。
何に気づいていないのかわからなくて、僕は問い返すことしかできない。
リーリエの後ろに回り込んで立ち、その両肩に手を乗せた遠坂は、言った。
「この子、百合乃ちゃんだよ」
「は? え?」
突然あり得ないことを言われて、僕はリーリエの顔を見つめること以外、まともな反応ができない。
「何言ってんだよ、遠坂……」
力なく反論しようとするけど、僕が見ている間に、笑みを浮かべていたリーリエの顔が、悲しみに歪む。涙を流し始める。
「……本当に、久しぶり。おにぃちゃん」
僕に近づいてきて、ピクシードールの特徴であるふた回り大きな手で、服の裾をつかむ彼女。
「あのとき、ちゃんとお別れ言ったのにね。こんな身体で、戻ってきちゃった……」
――あぁ、そうか。
どうすることもできず、中途半端に伸ばした僕の手に、うつむいた彼女の流す涙がぽたぽたと降ってきていた。
リーリエが願いを叶えた後から微かにあった、違和感。
顔を上げ、泣きながら笑っている顔を見せる彼女の言葉に、僕はその答えを見つけた。
「百合乃、なのか?」
「うん、おにぃちゃん。ゴメンね。ただいま」
小さな身体で抱きついてきたリーリエ。いや、百合乃。
僕はその身体を抱き締めながら、理解していた。
――リーリエの願いは、百合乃の復活だったんだ。
根拠もなく、僕はリーリエの願いが人間になることだと思っていた。
直接彼女に、訊くことができなかった。
そしてたぶん、もう二度とそれを訊く機会を失ったのだと、僕はそのとき知った。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました
フルーツパフェ
大衆娯楽
とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。
曰く、全校生徒はパンツを履くこと。
生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?
史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。



幼なじみとセックスごっこを始めて、10年がたった。
スタジオ.T
青春
幼なじみの鞠川春姫(まりかわはるひめ)は、学校内でも屈指の美少女だ。
そんな春姫と俺は、毎週水曜日にセックスごっこをする約束をしている。
ゆるいイチャラブ、そしてエッチなラブストーリー。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

GAME CHANGER 日本帝国1945からの逆襲
俊也
歴史・時代
時は1945年3月、敗色濃厚の日本軍。
今まさに沖縄に侵攻せんとする圧倒的戦力のアメリカ陸海軍を前に、日本の指導者達は若者達による航空機の自爆攻撃…特攻 で事態を打開しようとしていた。
「バカかお前ら、本当に戦争に勝つ気があるのか!?」
その男はただの学徒兵にも関わらず、平然とそう言い放ち特攻出撃を拒否した。
当初は困惑し怒り狂う日本海軍上層部であったが…!?
姉妹作「新訳 零戦戦記」共々宜しくお願い致します。
共に
第8回歴史時代小説参加しました!

【R18】俺は変身ヒーローが好きだが、なったのは同級生の女子でした。一方の俺は悪の組織に捕らえられマッドサイエンティストにされた
瀬緋 令祖灼
SF
変身ヒーロー好きの男子高校生山田大輝は、普通の学生生活を送っていたが、気が晴れない。
この町には侵略を企む悪の組織がいて、変身ヒーローがいる。
しかし、ヒーローは自分ではなく、同級生の知っている女子、小川優子だった。
しかも、悪の組織に大輝は捕まり、人質となりレッドである優子は陵辱を受けてしまう。大輝は振り切って助けようとするが、怪人に致命傷を負わされた。
救急搬送で病院に送られ命は助かったが、病院は悪の組織のアジトの偽装。
地下にある秘密研究所で大輝は改造されてマッドサイエンティストにされてしまう。
そんな時、変身ヒーローをしている彼女、小川優子がやって来てしまった。
変身ヒーローの少女とマッドサイエンティストの少年のR18小説
実験的に画像生成AIのイラストを使っています。
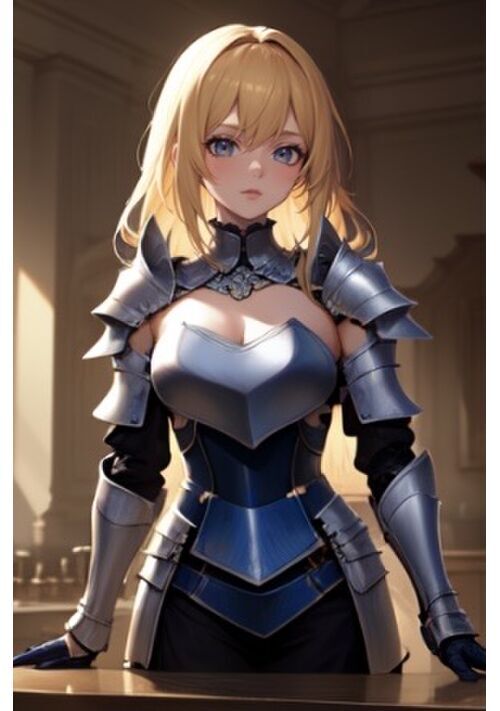
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















