115 / 150
第六部 第一章 レストレーション
第六部 暗黒色(ダークブラック)の嘆き 第一章 3
しおりを挟む* 3 *
「ただいま」
鍵を開けて部屋に入った夏姫は、コートを脱ぎながら克樹の方を見る。
暖房もつけず、頭を抱えた格好で部屋の隅に転がっている彼。
学校などから帰ってきたとき、部屋で待っている人がいるということが最初は暖かくも感じたが、もうそろそろ二週間が経ついま、心配の方が強くなってきていた。
コートを脱いでハンガーに掛けた夏姫は、制服のまま畳に座った。
「克樹、話があるの。座って」
わずかに身体を動かすものの、克樹は夏姫の声に応じてはくれない。
彼の背中を睨みつけ、夏姫はもう一度言う。
「座りなさいっ、克樹!」
鋭い言葉で言うと、身体をびくつかせた克樹は、ゆっくりとした動作で身体を起こす。
軽くあぐらを掻いた格好で座った彼だったが、うつむいて夏姫の顔を見ようとはしない。
「克樹はこれから、どうするつもりなの?」
「……」
うつむいたままの克樹は、夏姫の問いに答えない。
口を強く引き結んだまま、喋ろうともしない。
「あのとき、残りのエリキシルソーサラーがわかった、って言ってたよね? それは誰なの?」
そう問うと、克樹は顔を上げた。
泣きそうなくらい顔を歪ませている克樹は、それでも何も言ってくれなかった。
夏姫には、残りのエリキシルソーサラーが誰なのか、推測はついていた。いまの反応と、あの日リーリエに問うていたことを考えれば、克樹が言わない理由もわかる。
けれどもはっきりと、克樹の口から答えが聞きたかった。
それがたぶん、克樹がもう一度立ち上がる一歩となるだろうと思えていたから。
――このままじゃダメなこと、わかってるよね?
心の中で、目を逸らしてしまった克樹にそう問いかける。
このままではいられないことは、克樹もわかっていることのはずだった。リーリエを遠ざけて、何もせずに転がっていても、勝手に解決することはない。
少なくとも、望み通りの結果が得られることはない。
結果が出てからも動かなくてはならないことも変わりないし、いつかは自分の足で動き出さないといけない。
平泉夫人のことを考えれば、そのことがひと段落してからとも思いもしたが、近く夫人のことに結果が出るのだとしたら、それは最悪のものになるかも知れなかった。
どうなるかわからないにしても、最悪の結果が出るよりも先に、いまのうちに動かなければならないだろうと、夏姫は考えていた。
「克樹はこのまま、待つだけなの? このままじゃいけないこと、わかってるよね?」
「……それは、わかってるけど」
目を逸らしたままの克樹は、口の中でもごもごと答える。
深くうつむいた彼が迷っているのは、これまで見てきたからわかっていた。そして迷いながらでも、動いてくれる人だということも、夏姫は理解していた。
いまはいろいろあって、そのための一歩が踏み出せなくなってしまっている。
――だったら、アタシがやるべきなのは、こいつの背中を押してやることだ。
そう思った夏姫は、克樹に語りかける。
「パパが大変だったとき、アタシは克樹に支えてもらったよ。助けてもらったよ。克樹から、たくさんのものをもらったよ。だから、いまはアタシが克樹のことを支えていたいと思う」
あのときの感謝と、嬉しい気持ちを込めて、夏姫は克樹のことを見つめる。
話してる間に、彼もまた、うつむかせていた顔を上げてくれる。
「アタシは、克樹のことが好き。大好き。克樹もアタシのこと、好きだよね?」
「……うん」
「ママが亡くなって、パパも帰ってこなくて、アタシはひとりで過ごしてて、それで大丈夫だと思ってた。でもね? 克樹。本当はアタシは寂しがり屋だった。克樹と一緒にいるようになって、それを感じたの。克樹に支えてもらって、やっぱりアタシはひとりじゃいられないって思ったの」
話してる間に、胸にこみ上げてくるものがあった。
喉を通り過ぎたそれは、目頭を熱くして、いつしか克樹の顔が揺らいで見えるようになる。
「だから、アタシは克樹がしてくれたように、貴方のことを支えたい。いまが大変な状況だってのはわかるよ。でも、このままじゃいけないのも、わかってるよね? もし、ひとりじゃ踏み出せないなら、アタシが手伝うよ。アタシが、克樹と一緒にいるよ」
そこまで言った夏姫に、克樹が息を飲むのが見えた。
彼に手を伸ばすと、手を握って引き寄せてくれた。
そのまま抱き締められる。
「ありがとう、夏姫」
「うん……」
克樹の身体に腕を回すと、彼の身体が細かに震えてるのがわかった。
暖かい胸からでは見えなかったが、何度も何度も喉を詰まらせているらしい彼が、泣いてるのもわかった。
そんな克樹のことを、夏姫は強く、強く抱き締める。
抱き締めてくれる彼のことを、精一杯の力で抱き締めていた。
「――聞いてくれ、夏姫」
「うん」
「もしかしたら、平泉夫人は長くないかも知れない」
「え?」
身体を離した克樹の顔を見ると、目尻に涙を溜めていた。
「本当に?」
「はっきりしたことは、芳野さんからは聞いてない。でも、毎日通ってるからね、さすがに僕でもわかるよ。弾丸は摘出できたけど、容態がよくなってない。奇跡でも起きない限り、平泉夫人はたぶん、もう――」
「そんな……」
そうであることを、予想していなかったわけではなかった。
いまだ意識を取り戻していない平泉夫人。
このままいけばどうなるかは、夏姫でもわかることだった。
けれどもそれをはっきり言われると、さすがにショックを隠すことができない。
「夏姫に迷惑かけてることはわかってる。でも、でももう少しだけ、平泉夫人がどうなるのかはっきりするまでは、待っていてほしい」
「それは、いいけど……」
「せめて意識が戻れば、もう少しどうにかなるかも知れないらしいんだけど、ね……」
うつむいた彼の様子から、それが難しい状況なのはわかった。
克樹に紹介してもらってからそれほど長くないとは言え、たくさん世話になった人が長くないかも知れないと知ると、なんと言っていいのかわからなかった。
克樹の頬に手を添え、彼のことを抱き締めようとしたとき、制服のポケットに入れておいた携帯端末がけたたましい着信音を響かせた。
悲しそうな目で頷く克樹に、夏姫は携帯を取りだし、芳野さんからだった着信に応答する。
「はい……。え? は、はいっ。克樹、替わってほしいって」
静かな口調なのにどこか焦った様子の芳野に替わってほしいと言われ、夏姫は克樹に携帯を差し出した。
「――はい、音山、克樹です。……え? それはっ! す、すぐに向かいます!!」
話の内容は聞こえなかった。
けれども驚いた顔になる克樹に、何かがあったことだけは理解した。
「どうしたの? 克樹」
「いや、ちょっと……。これから病院に行ってくるっ」
差し出された携帯端末を受け取りながらそう問うと、驚いた顔の彼にそう言われた。
「大丈夫、なの?」
「えっと……、と、とりあえず後で報告する!」
慌てた様子の克樹は、それだけ言って玄関へと向かっていった。
靴を履ききらないまま転がるように外に出て行く彼の背中を見ながら、夏姫は心配で仕方がなかった。
*
強い消毒液の匂いに鼻を刺激されて目を開ける。
真っ白な天井には憶えがなく、首を動かすのすら億劫ながらも、辺りを見回してみて、自分のいる場所を知る。
「あの人の元へは、行けなかったみたいね。残念だわ」
一度大きく深呼吸をした平泉夫人は、口を覆うマスクを外し、上半身を起こした。
途端に身体の何カ所かで走る痛み。
あの日、銃撃を受けてから何日が経っているのかはまだわからなかったが、傷が治りきるほどの時間は経っていないらしい。
「あの子たちに感謝しなければならないわね。まだやってほしいことがあるようだけれど」
眠り通しで曇っていた思考は痛みですっかり晴れ、平泉夫人は改めて周囲を見渡す。
病院の、おそらくVIP用の病室。時間はそろそろ夕方だろうか。
心拍計などの病院の機材の他に、夫人が仕事で使うような機材は置かれていない。しかし、サイドテーブルにはタブレット端末が置かれていた。
自宅でも使っている見慣れたそれを取り、表面に指を滑らせて起動する。
日付と時間を確認した夫人は、オフラインながらいつも芳野と報告のやりとりをするのに使っているアプリを立ち上げた。
病院ではネット環境を整えきれなかったのだろう、けれど毎日情報を更新して持ち込んできている様子のタブレット端末には、夫人が起きてすぐにほしいと望む情報が、コンパクトにまとめられていた。
いつもの芳野ならばそれ自体は造作もない仕事。
ただ、夫人が倒れていて、それも生死の境にある期間ということと、情報のまとめ方、それから添えられた文章の細部に、小さな変化を発見していた。
詳細を見るのは後回しにして、一覧性重視でまとめられた情報にひと通り目を通し終わる頃に、大きな駆け足の音が聞こえてきた。
「奥様!」
「早かったわね、芳野。けれどここではもう少し静かにしてもらえるかしら?」
「は、はい……」
顔を大きく歪めて、泣きそうになっている芳野。
叱られた犬のように肩を竦めて小さくなっている彼女に、平泉夫人は笑いかけた。
「心配かけたわね。もう、私は大丈夫よ」
「奥、様……」
近づいて来、ベッドに突っ伏して肩を震わせる芳野の髪を、優しく撫でてやる。
襲撃を受けてから十一日。
ずいぶん長い時間が経ち、芳野にはかなりの心配をかけてしまったと思ったが、大丈夫そうだった。
顔を上げ、顔を引き締めた芳野は言う。
「まだ目が覚めたばかりです。昨日の夜までは危険な状態だったのですから、もう少しお休みください」
「そうしたいところだけれど、いまは大丈夫よ。無茶はできないけれどね。それに、私は与えられた役目を果たさなくてはならないわ」
「役目、ですか?」
居住まいを正した芳野が眉を顰めるのに、夫人は微笑みで返した。
「いまの私は、命を救ってもらったのよ。もう役目は終わったのだと思っていたのだけれどね……。私自身の意向を、汲み取ってくれる気はないようね」
「それはどういう?」
首を傾げている芳野に、夫人は詳しく説明したりはしない。
夫人自身も何があったのかわかっているわけではなかった。それでも、離れていくはずだった命を、誰がつなぎとめてくれたのかはわかっていた。
「私はもらったものは、最低でも三倍で返す主義なのは、知っているでしょう? それが恩でも、――仇でも」
「はい……」
「宣戦布告に対して、攻撃を受けた。その分で三倍。死ぬはずだったわたしをつなぎ止めてくれた子たちの分で三倍」
唇をつり上げ、平泉夫人は攻撃的な笑みを浮かべる。
「これからは、私たちのターンよ。恩と仇の分で九倍、あの魔女に返すわよ。――反撃に移るわ、芳野」
虚を突かれたように目を見開いた芳野は、しかし直後に拳を握りしめ、輝き始めた夫人の瞳を真っ直ぐに見つめる。
「はい!」
「とりあえず検査があるでしょうけれど、それが終わったらすぐに仕事にかからなければならないわ。魔女がこちらの反撃に気づく前に、充分に仕掛けをつくっておかなくては」
「わかりました。すぐに必要な機材をこちらに移します」
「それから、克樹君を急いで呼んでちょうだい。あの子とは、いますぐにでも直接会って、話をしなければならないわ」
「はい。連絡いたします。それでは」
病室に入ってきたときの泣きそうな様子はなく、すっかり平常運転に戻り、一分の隙もない動作で踵を返し病室を出て行こうとする芳野の背中に、夫人は声をかける。
「それから芳野。これは急ぎではなく、ひと段落してからで良いのだけれど――」
「はい」
振り返って引き締まった顔で言葉を待つ彼女に、夫人は笑みを浮かべながら言った。
「彰次さんを、連れてきてくださいね」
「……はい」
顔色も、表情にも変化はなかったが、芳野の答えがほんのわずかに遅れたことを、夫人が気づかないはずもなかった。
「あの人を呼ぶ理由は、説明しなくてもわかるわよね?」
「……」
メイド服のエプロンの前で組まれた手が、明らかに震え始める。うろたえている。
質問に答えないのではなく、答えられないほど混乱している様子の芳野に、平泉夫人は小さく笑い声を漏らしていた。
彰次と芳野が惹かれあっているのは、傍目から見ても明らかだった。
結末まではわからないにしても、いつかはその距離を縮める手伝いをしようかと思っていた矢先の、魔女からの攻撃。それがあることも考えて、芳野のことを本家に頼んでいた。
まだ、彰次に芳野のことを頼むには、早すぎると思っていたから。
もし自分が早々に殺されることがあったら、芳野の心は折れてしまうと想像していた。
彰次は芳野の支えになろうとすることは予想できたが、彼女にはまだ彼を受け入れる準備ができていないだろうと思った。
それなのに、目覚めてすぐ見つけたタブレット端末には、芳野らしい仕事がキッチリとこなされていた。
自分が死なずにいたからということもあるだろうが、最初の数日は神経をすり減らす時間ばかりであったはずなのに、それを乗り越えている様子に、彼女の支えた人物の存在を感じた。
音山彰次以外には、考えられなかった。
――私の想像など、超えて行ってしまうのね。
娘にも近い存在である芳野が、いつのまにか変化し、成長していることに、嬉しさと、一抹の寂しさを感じながら、平泉夫人は笑む。
「貴方は私の可愛い娘なのですからね。彰次さんにはしっかり挨拶してもらわなければならないわ」
「……わかりました。折りを見て、お呼びいたします」
「えぇ、頼むわ。それよりもまずは、克樹君をお願いね」
「はい」
答えて芳野は病室を出て行った。
残された平泉夫人は、ひと通り見終わったタブレット端末をテーブルに置き、身体をベッドに横たえさせる。
「私はあの子から、克樹君の背中を押すように頼まれてしまったのですからね」
そう言って夫人は、笑みを浮かべていた。
*
受付を通り抜けて廊下を走り、階段へと向かう。看護師さんの注意の声が聞こえてきたのは、階段を昇り始めた後だ。
最上階、VIP専用病室前のセキュリティゲートには、ガタイのいい男性がふたり。挨拶もそこそこに、ゲート下のエアクリーナーの風で埃を落とし、消毒を受けてから目的の病室へと向かった。
一気に扉を開けると、すぐに見えたベッドの人物。
上半身を起こして微笑んでいる、入院着姿の平泉夫人。
「お待ちください、克樹様」
思わず駆け寄ろうとしてしまった僕を止めたのは、芳野さんの腕。
睨みつけてくるような厳しい視線の彼女は、近くの椅子を引き寄せて僕の前に置いた。
「ごめんなさいね、克樹君。喜んでくれるのは嬉しいのだけれど、目覚めたばかりでまだ無理ができる身体ではないのよ。それに、病院では静かにね」
「はい……」
椅子に座りながら、僕は少しかすれた感じのある、でも聞き慣れた平泉夫人の声に、思わず泣きそうになっていた。
死んでしまうと思っていた。
もう二度と、その声を聞くことはないと思っていた。
大切な人を失うんだと、諦めていた。
それなのにいま、平泉夫人は以前と変わらない優しげな笑みを、僕に投げかけてくれる。
――こんなに嬉しいことがあるだろうか。
胸の奥からこみ上げてくるものが抑えきれなくなりそうで、僕は唇を噛みながら、膝の上で両手を強く握って堪えていた。
「いろいろと、大変なことがあったようね」
その言葉に、僕の中からこみ上げていた感動は、一気に冷え切ってしまう。
優しげな笑みはそのままなのに、夫人の瞳に映っているのは、冷たさを感じるほどの鋭さ。
「詳しい話を聞きたいのだけれど、面会時間も限られていますからね。週末には一時帰宅の許可を取るつもりだから、そのときに聞かせてもらうことにするわ」
「はい……、わかりました」
いまこの場で話さなくてよくなったことに、僕はこっそりと安堵の息を吐く。
リーリエのこと、エイナのこと、エリキシルバトルやモルガーナのことなどは、まだ僕の頭の中でぐちゃぐちゃと形をなしてなくて、上手く話せる気がしない。
「と、とにかく、平泉夫人が目を覚まして、本当に良かった……」
自分の言葉で再びこみ上げてきたものに、僕は抑えきれず涙が溜まるのを感じていた。
差し出された夫人の左手に両手を伸ばし、強すぎないように握る。
暖かさが、嬉しかった。
確かに生きているのだと、実感できた。
芳野さんからの連絡で目を覚ましたと言われても、いまひとつ信じられなかったのに、いまやっと、夫人が生きて、こうして僕と話せるようになったのだと、感じることができた。
不安が、一気に晴れた。
「本当は、あのまま死んでしまうのも良いと思っていたのだけれどもね」
「夫人!」
「奥様!」
僕と芳野さんの声は同時。
いくら平泉夫人でも、死んでいいなんて言葉は反発せずにはいられない。
ふたりの鋭い視線を受けながらも微笑んでいる夫人は言う。
「さすがにいまはそんなことは考えていないわ。けれど私は、あの人の元に行きたいと、いつも思っていますからね」
「……死後の世界を、信じているわけではないでしょうに」
「えぇ、そうなのだけどね。あの人と別れて、少し時間が経ちすぎてしまったわ。けれどいまは、やり残したことが多くて。それに託されたものがあるから。そんなことはもう考えていないわ。――さて、本題に入りましょうか」
優しげで、悲しげでもあった表情を引き締めた平泉夫人に、僕はまだ握っていた手を離して椅子に座り直した。
夫人が目覚めたその日に、報告ではなく呼び出しを受けたのには、何か用事があってのことだとはわかっていた。
覚悟なんてしてる余裕はなかったけれど、夫人の言葉をしっかり受け止められるよう、気持ちを落ち着かせる。
「起こったことの詳細は聞いていないけれど、芳野から貴方の様子については聞いたわ。――リーリエちゃんのことが、信じられなくなった?」
「なんで、それを……」
起きたことを知らないと言って、芳野さんからの話だけでそんなことを言ってくる夫人の真意が、わからなかった。
確かにリーリエとの接触を避けているのは、いつもつけていたイヤホンマイクがないのを見ていれば気づくかも知れない。でもそれがあいつのことを信じられなくなったからだなんてのは、どうしてわかるんだろうか。
驚いてる僕を見透かしたように微笑む夫人は言う。
「真実は直接当事者から聞くことにするけれど、私でも推測くらいはできるのよ。それから克樹君のことは、夏姫さんの次くらいにはわかってるつもりよ」
「うっ」
唐突に出てきた夏姫の名前に、僕は夫人の観察力と推測力の高さを知る。
夏姫との関係は、一緒に夫人の屋敷に訪れることが多かったんだ、バレてない方がおかしいだろう。
けれど夫人が推測しているのはさらにその先、いまの僕と夏姫の関係にまで踏み込んでいるように思えて、何も言えなくなる。
「克樹君。貴方はこれまで、リーリエちゃんのことを、道具のように思ってこなかったかしら? もちろん全部というわけではないでしょうけれど、あの子をひとりの人間として、ひとつの個性として捉えてこなかった。違う?」
「……それは、そうかも知れません」
認めるしかなかった。
口元は微笑んでいるのに、僕の奥底まで覗き込くような瞳を向けてくる平泉夫人には、嘘も誤魔化しも利かない。
頭では理解していた。
身体は持たず、仮想のものであってもひとつの脳を持つリーリエは、僕たち人間と同じ精神を持つ存在なのだ、と。
でも同時に、僕はリーリエのことを道具のように扱っていたことも事実だ。
信頼していた。
百合乃に似ていて、けれど少し違うリーリエのことが、可愛いとも思っていた。
そんな人間的なところを認めていながら、仕事を頼んだりとか、道具のように扱っていたと、自分でも思う。
そうした関係は、僕だけじゃなく、リーリエもが求めて成立してきたものだろう。身体を持つ人間の僕と、身体を持たない人工個性のリーリエとで築き上げてきた、ふたりの立ち位置だった。
いつからだったのか、もしかしたら一番最初、リーリエが起動したときからか、僕は彼女を心のどこかで高度な人工知能のような扱いをしてきたと、いまさらながらに思い至る。
平泉夫人に指摘されて、改めて僕はそれを知る。
「なんで……、そんなことがわかるんですか」
「克樹君はずいぶん家に帰っていないようだと聞いていたからね、予想はつくわ」
見透かしたような瞳に心配の色を浮かべながら、夫人は笑む。
昏睡状態から目覚めたばかりで、詳しいことは話していないから情報だって不足してるはずなのに、夫人はどこまで凄いというのだろう。
僕は夫人に、思いの丈を話す。
「僕は……、どうしたらいいのかわかりません。リーリエのことを信じられなくなったのはあるけど、でもそれだけじゃなくって……」
ここのところずっと考えていて、でも少しも考えがまとまらなかった。
平泉夫人のことは大き過ぎて、心配と不安で食事もあんまり喉を通らなかった。
リーリエがエリキシルソーサラーで、僕の敵となる存在だったのは、本当にどうにもならないくらいのことで、生きることすらイヤになるほどだった。
でもそれだけじゃなくって、その前からずっと一緒だったリーリエのことも浮かんできて、学校に行くこともできなくなっていた。
夏姫に言われた通り、このままじゃいけないのもわかっているのに、動くことができなかった。
泣けばいいのか、叫べばいいのかわからないこの気持ちは、唇を噛んでも抑えきれないのに、どうやって吐き出せばいいのかも思いつけなかった。
「悩んでいるときは、ひとつひとつ、手に触れたものから片付けていけばいいのよ。でも自分だけでは解決できない問題もあるし、大き過ぎる問題は、立ち向かうだけでも覚悟が必要ね」
「……そうですね」
僕のことを優しい笑みで見つめてきてくれていた平泉夫人は、ニッコリと笑む。
「ただね、克樹君。リーリエちゃんは、これまで貴方の期待に応えてくれなかったことは、あるかしら?」
「リーリエは……、僕を、裏切りました」
「本当にそうかしら? 裏切られたと感じるのは、あの子のことを、ひとりの人間として捉えてこなかった、克樹君に原因があるんじゃないかしら?」
「どういうことですか?」
リーリエが僕を裏切って、エリキシルソーサラーであることを黙っていたのは事実だ。それ以外であるはずがない。
楽しそうな笑みを浮かべながら、でもどこか、先生とか、僕には縁遠い存在だけど、母親を思わせる瞳で、平泉夫人は言う。
「例えばだけど、克樹君は夏姫ちゃんのことは、好き?」
「え? そ、それは……。はい、好き、ですけど」
突然違う方向に飛んでいった問いに、僕は顔が熱くなるのを感じながらも、素直に答える。
「でも夏姫ちゃんも、エリキシルソーサラーでしょう? 克樹君とは違う願いを持って、戦ってる。それでも貴方は、彼女のことが好きで、信頼しているの?」
「……はい、その通りです」
何となく、夫人の言いたいことがわかってきた気がした。
夏姫の最初は敵として戦ったエリキシルソーサラーで、でもいま僕は彼女のことが好きだ。信頼もしてる。
そうでなきゃ、アパートの部屋に転がり込んだりなんてできない。逆に夏姫も僕のことを同じように信頼してくれているから、部屋にいることを許してくれてるんだろう。
「人はね、誰だって嘘は吐くし、秘密を持つわ。それがどんなに大切な人に対してであっても、ね。むしろ大切だからこそ言えないことも、言わないこともある、なんてこともよくあることよ」
夫人から伸ばされた手が、僕の手を包んだ。
まるで抱き締められているような手の感触に、僕はそれまでぐしゃぐしゃで、どうにもできなかった頭の中が、整理されていくのを感じていた。
「貴方はリーリエちゃんのことを、私や夏姫ちゃんのように、ひとつの人格だと理解していながら、実感するところまではできていなかった。身体を持っていなくても、あの子は私たちと同じ人間。嘘も吐けば、秘密も持つ、ひとりの女の子よ」
「そう、ですね……」
改めて言われて、僕は自分がどれほどリーリエのことを甘く見ていたのかを実感する。
知識としては知っていて理解してるのと、実感してるのとじゃ、大きく違っていた。
いまはリーリエに謝りたい気持ちでいっぱいだった。
――でも……。
やっぱり裏切られたんだという気持ちが消えることはない。
リーリエにどんな顔を見せればいいのか、見せることになるのか、わからない。
「克樹君の願いは、貴方の復讐心によるものだけど、それは百合乃ちゃんが大切だからこそ出てきたものでしょう?」
「はい……、その通りです」
「リーリエちゃんの願いまではわからないけれど、貴方の見てきたあの子は、どんなことを願いそうな女の子かしら?」
微笑みとともにそう問われて、僕は考え込む。
ずっと僕と一緒にいてくれたリーリエ。
僕の願いを知りながら、否定するような言葉をかけてくることは一度もなかった彼女。
ひとりの女の子としてのリーリエは、どんなことを想い、何を願うだろうか。
起動してから本当にずっと一緒にいたリーリエなのに、僕にはそれを思いつくことができなかった。
「リーリエちゃんはね、誰よりも克樹君のことが好きな女の子よ。いますぐには信頼しろなんてことは言えない。けれど、もう一度あの子のことを、ひとりの人間としての、女の子としての彼女を、見つめ直してみてもいいんじゃないかしら?」
「――はい」
泣きそうだった。
一番身近な存在のことをぜんぜん知らなかったなんて、悲しすぎる。
リーリエがこんな僕のことをどう思ってるのか、不安だった。
だから僕は、さっきまでとは違うこみ上げてくるものを、鼻をすすりながら飲み込む。
「週末、呼べる関係者を全員屋敷に呼んで、話をしましょう。連絡はこちらでしておくわ。だからそれまで、克樹君はリーリエちゃんのことを、それから自分のことを、見つめ直していなさい」
僕はいま、自分がどれだけ子供なのかを知った。
平泉夫人と話して、ずっと処理できなかった気持ちが、一気に晴れ渡ってしまったのだから。
考えなくちゃいけないことがなくなったわけじゃない。
でもいまは、平泉夫人に助けてもらった僕は、一歩先に進めそうだと、そう思えた。
「わかりました」
目を細めて嬉しそうに笑う平泉夫人に、僕は力強く頷きを返していた。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました
フルーツパフェ
大衆娯楽
とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。
曰く、全校生徒はパンツを履くこと。
生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?
史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。



幼なじみとセックスごっこを始めて、10年がたった。
スタジオ.T
青春
幼なじみの鞠川春姫(まりかわはるひめ)は、学校内でも屈指の美少女だ。
そんな春姫と俺は、毎週水曜日にセックスごっこをする約束をしている。
ゆるいイチャラブ、そしてエッチなラブストーリー。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

GAME CHANGER 日本帝国1945からの逆襲
俊也
歴史・時代
時は1945年3月、敗色濃厚の日本軍。
今まさに沖縄に侵攻せんとする圧倒的戦力のアメリカ陸海軍を前に、日本の指導者達は若者達による航空機の自爆攻撃…特攻 で事態を打開しようとしていた。
「バカかお前ら、本当に戦争に勝つ気があるのか!?」
その男はただの学徒兵にも関わらず、平然とそう言い放ち特攻出撃を拒否した。
当初は困惑し怒り狂う日本海軍上層部であったが…!?
姉妹作「新訳 零戦戦記」共々宜しくお願い致します。
共に
第8回歴史時代小説参加しました!

【R18】俺は変身ヒーローが好きだが、なったのは同級生の女子でした。一方の俺は悪の組織に捕らえられマッドサイエンティストにされた
瀬緋 令祖灼
SF
変身ヒーロー好きの男子高校生山田大輝は、普通の学生生活を送っていたが、気が晴れない。
この町には侵略を企む悪の組織がいて、変身ヒーローがいる。
しかし、ヒーローは自分ではなく、同級生の知っている女子、小川優子だった。
しかも、悪の組織に大輝は捕まり、人質となりレッドである優子は陵辱を受けてしまう。大輝は振り切って助けようとするが、怪人に致命傷を負わされた。
救急搬送で病院に送られ命は助かったが、病院は悪の組織のアジトの偽装。
地下にある秘密研究所で大輝は改造されてマッドサイエンティストにされてしまう。
そんな時、変身ヒーローをしている彼女、小川優子がやって来てしまった。
変身ヒーローの少女とマッドサイエンティストの少年のR18小説
実験的に画像生成AIのイラストを使っています。
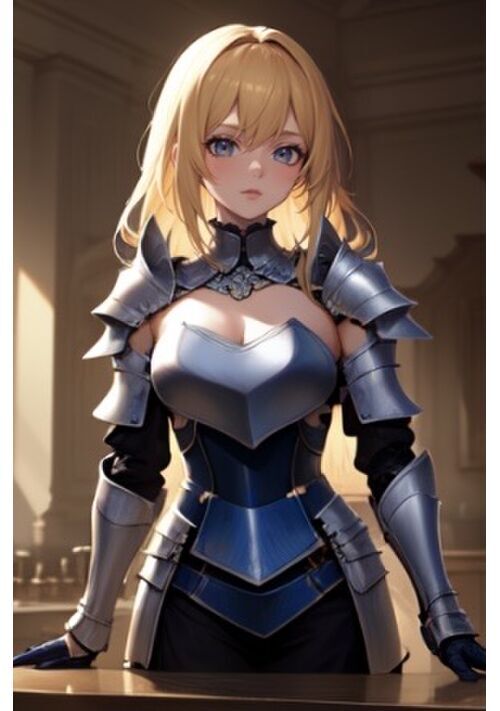
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















