111 / 150
第五部 終章 マイソロジー
第五部 撫子(ラバーズピンク)の憂い 終章
しおりを挟む終章 マイソロジー
*
チェストの引き出しを開けた夏姫は、ブラウスのボタンを外しながらしばし考え込む。
――今日は、克樹のとこ行かない方がいいのかな。
昨日、ニュースを見てから呆然として、何もできなくなっていた克樹。
無理矢理せき立てて服も着替えさせず、ベッドに押し込んで家に帰った。今日の朝早くに見に行ってみたら、ずっと同じ格好で、眠ってすらいないようだった。
学校に行くことはできなさそうな克樹を残して登校したが、昼頃に夫人の収容された病院がわかったから行ってくるというメールが入っていた。
平泉夫人の容態ももちろん気になっていたが、夏姫は自分にとって身近な、克樹のことが気になっている。
唇を引き結び、開けた引き出しの中も見ずに夏姫は彼のことを思う。
学校帰りに彼の家に寄ってみると、リーリエにはまだ帰っていないと言われ、昨日何があったのかを訊いても答えてもらえなかった。
克樹のことが気になりながらもバイトを終え、アパートの部屋に帰ってきた夏姫は、どうするべきか考えてしまう。
彼のことだから、夕食はまともに食べていないだろう。
それどころか、昼食も、つくって置いておいた朝食も食べたかどうか怪しい。
気持ちが沈んでいるときは食事を摂る気力も、摂ろうという発想もなくなってしまうのは仕方ないが、それではダメなことは、自分の父親が生死の境を彷徨ったときに、夏姫が感じたことだった。
――たぶん、平泉夫人は克樹にとって、母親みたいな存在だったんだろうな。
振り返った夏姫は、机の上の充電台に置いてある、春歌が残してくれたブリュンヒルデのことを見つめた。
克樹の両親については、彼があまり話したくなさそうにしていたのもあって、詳しくは知らない。
けれど彼と出会って一年ほどが経っているにも関わらず、一度も家に帰ってきたことはなく、帰ってくるという話も聞いたことがなかった。
叔父の彰次が保護者になっていることを考え合わせると、家族として成立していないのはわかる。
そんな中にあって、呼び出されたりもしているけれど、呼んでくれて話を聞いてくれ、何かと心配してくれる平泉夫人は、克樹にとって両親よりも大きな存在であろうことは想像に難くない。
家族と言うほどには接近せず、お互い一線を引いたつき合いをしてはいるが、もしかしたら平泉夫人は克樹にとって、彰次やリーリエ、そして夏姫よりも距離の近い人物なのかも知れなかった。
そんな夫人がいま、生死の境を彷徨っている。
その事実は、克樹をあれほど憔悴させるに足るものだったのだろう。
――やっぱりもう一度、克樹のとこに行ってこよう。
もう遅い時間だが、外着に着替えようとしていたとき、チャイムが鳴った。
「誰だろ」
ブラウスのボタンを留め直しながら玄関に近づいていき、セールスだったら無視しようと思いつつドアスコープで訪問者を確認する。
「克樹?!」
扉の向こうにいたのは、朝よりも少しマシに見えたが、暗い顔をした克樹。
急いで鍵を外して扉を開けると、夏姫に目を向けているのに、夏姫のことを見ていない彼は、声もかけずに部屋に入ってくる。
靴を脱ぎ捨て、ふらふらと部屋に入っていく克樹を追って、玄関の鍵をかけた夏姫は部屋に戻った。
「どうしたの? 克樹っ」
部屋の真ん中で座り込んでしまった彼に強めの口調で呼びかけてみるが、顔を上げはしたが、その口からは何も言葉が出てこなかった。
「ねぇ!」
強い声を出してみても、泣きそうに顔を歪め、唇を震わせるばかりで、克樹は何も言ってはくれない。
何かがあったのだとしたら、まずは話を聞かなくてはならない。
自分のとき、何も言えないでいたのに、克樹は言葉を引き出してくれた。
彼ほど上手くはできないけれど、とにかく話を聞いて、それからでなければ自分に何ができるかが考えられない。
「もしかして、夫人は……」
「それは、まだ」
ふと思いついて口にした言葉に、克樹は返事をくれた。
そこからとにかく言葉を引き出そうと、夏姫は彼に問う。
「平泉夫人の容態は、じゃあいまはどうなの?」
「まだ、わからない。あと一回手術が必要なんだけど、容態が安定しないからどうにもできてない。何か変化があったら、芳野さんかショージさんから連絡もらえるように言ってある」
「そっか」
少し詰まりつつも、克樹はしっかりした口調で話してくれた。
彼の正面に座り、何もできない夏姫はぎこちなくあったけれど、笑いかける。
「じゃあ、待ってるしかないね。すぐに駆けつけられるように、食事摂って、ちゃんと寝ないと」
「うん……」
夏姫の笑みでも、克樹の表情の曇りは晴れない。
昨日からの一日で、頬がこけてしまっている感じすらある克樹は、さらに暗い表情になる。
「……他にも、何かあったの?」
「……」
「昨日、残りふたりのエリキシルソーサラーがわかった、って言ってたよね。そのこと?」
「……」
夏姫の言葉に大きく目を見開いた克樹は、でも何も言わずに視線を逸らす。
「リーリエ! 昨日何があったの?!」
克樹が答えてくれないならと、夏姫はリーリエに声をかける。
昨日の様子から考えるに、克樹だけではなく、リーリエも残りのエリキシルソーサラーについて知っている様子があった。
「……リーリエ?」
反応のないリーリエにもう一度声をかけてみるが、返事の声すらなかった。
「全部、家に置いてきた。携帯もネットは切ってある」
つらそうな顔でそんなことを言う克樹の耳には、スマートギアを被っていないときはいつも着けているイヤホンマイクがなかった。
ポケットから取り出した携帯端末は、通話オンリーのモードになっていると表示されていた。
「何が――」
言いかけて、夏姫は言葉を止めてしまった。
夏姫はこれまで、克樹のことを情けない奴とか、イヤな奴だと思ったことはあった。
けれども、一度も弱い人だと思ったことはなかった。
泣いている姿も見たことはあったが、夏姫にとって克樹は、最初からずっと、強い人だった。
それなのにいまは、顔をくしゃくしゃにし、子供のように弱々しく身体を震わせている。
「僕はもう、何を信じればいいのかわからない……」
そんなことを言う彼に、夏姫はかけるべき言葉が見つからない。
決して全部を肯定できるような性格はしていないが、それでも夏姫を、他のみんなを引っ張ってくれた克樹は、その芯に強いものを持っている人だった。
彼を支えていたのは、平泉夫人や彰次などの大人たち。
そして何より、姿はなくても常に側にいた、リーリエだった。
それがいまは、夫人の先行きは見えず、自分からリーリエとの関係を断っている。
――何か、あり得ないことがあったんだ。
何かがあったことだけはわかったが、具体的な内容まではわからない。
そしていま、子供のように涙をぽろぽろと落とす克樹に、問うことはできなかった。
「大丈夫だよ、克樹」
言いながら夏姫は克樹の隣に身体を寄せ、彼の肩を抱き寄せる。
「アタシだってエリキシルバトルの参加者だから、克樹とも戦うこともあると思う」
嗚咽を必死で堪えている克樹の顔を覗き込み、夏姫は笑んでみせる。
「でもね? 克樹。アタシは克樹に、絶対嘘は吐かないよ。戦って、どっちかが勝っても、どっちかが負けても、アタシはずっと、克樹と一緒にいるよ」
「夏姫……」
「だから、大丈夫。安心して、克樹」
そう言った夏姫は、克樹の頬に手を添える。
震える彼の唇を、自分の唇で塞いだ。
「ね? 大丈夫だから」
「夏姫!」
しがみつくように覆い被さってきた克樹に押し倒される。
胸に顔を埋めて泣く彼を、抵抗することなく、夏姫は両腕を回して抱き締めた。
「好きだよ。愛してるよ、克樹」
涙に濡れた顔を上げた克樹に、もう一度キスをする。
克樹の不安を少しでも引き受けられるように。
克樹への想いをできるだけ伝えられるように。
長い口づけを終え、やっと涙が止まった克樹に、夏姫は微笑みを浮かべた。
そして彼に、頷いて見せた。
*
そこは広大な広間だった。
高い天井から降り注ぐ照明は明るかったが、床も、壁も、光を吸い込んでいるかのように黒い。
壁には等間隔に大きな調度品か何かが据え置かれている。しかし黒に沈むそれらは、明るい照明の下にあっても、輪郭がはっきりしていなかった。
空気は冷たく、静かで、少しも動いていない。
黒い床には黒い色で、細かな文様が描かれている。
その文様を踏みしめ、現れた人物。
赤いスーツを身に纏うモルガーナ。
広場に姿を見せた彼女は、その中心へと高らかなヒールの足音を響かせながら向かっていた。
中央にあるのは、四角い石の塊。
小型の家ほどもあるそれは、まるで墓石のようだった。
巨大であるのに傷ひとつ、つなぎ目ひとつない黒い立方体の側までたどり着いたモルガーナは、それに手をかざした。
途端、重々しい音とともに、石壁の中に石壁が入り込むようにして、内部への入り口が現れた。
照明もないのに天井が仄かに光るそこにモルガーナが入ると、入り口は振動とともに閉じられた。
狭い部屋のようになっている石塊の中あったのは、ひとつの台。
やはり黒いその台は、人が寝そべることができるほどに大きい。
「まさか、まだ早いはず……」
胸騒ぎに駆られて、彼女はこの場所を訪れていた。
眉根にシワを寄せ、モルガーナが台に手を着くと、天板がふたつに割れた。
左右に移動していく天板の代わりに、その下からせり上がってきたもの。
水晶玉。
人の頭ほどもある、黒い台に乗せられた水晶玉は、目を凝らさなければそこにあるのがわからないほどに透明度が高い。
オリジナルコア。
スフィアに内蔵されているクリスタルのすべては、このオリジナルコアの子種。
小型にしたとか、模倣したとかではなく、スフィアコアはオリジナルコアの欠片でできている。
「貴女は、もう目覚めているの?」
まるで人に話しかけるように、モルガーナはオリジナルコアに話しかける。
しかし冷たく光を反射するばかりで、コアから返事はなかった。
小さく息を吐いたモルガーナは、脇に置いてあった金色のハンマーを手に取る。
細かな文様のような、文字のようなものが隙間なく書き込まれたハンマーを頭上まで振り上げ、目をつむった彼女は小さく口の中で何かを唱える。
そして、振り下ろした。
澄んだ音が響いた。
硬い金属と、硬い石とがぶつかり合う音。
どんな楽器よりも美しく、破壊的な音を響かせながらも、オリジナルコアはほんの微かにも傷ついてはいない。
「やはり、もう無理ね」
ハンマーを置き、痛む右手を左手でさすりながら、モルガーナはそう呟く。
オリジナルコアを砕くことができなくなったのは、ひと月ほど前から。
砕いた欠片の使い方を思いついたのは半世紀近く前。
粉々に砕いてもしばらくすれば形状も、サイズも元に戻るオリジナルコアから欠片を採取し、スフィアのコアとして利用してきた。
スフィアは、第一世代からそのコアは変わっていない。
コアを包む外身の改良と、描いたシナリオに沿った演出によって性能や機能が変わってきただけだった。
しばらくの間は生産できるほどの在庫はあるが、欠片が採取できなくなったことで、そう遠くないうちにスフィアの出荷は止まる。
「もう時間がないわね」
じっとオリジナルコアを見つめるモルガーナは、複雑な表情を浮かべる。
スフィアが生産できなくなることなど、たいした問題ではなかった。
それよりも、オリジナルコアを砕けなくなった理由の方が問題だった。
「もうすぐ、目覚めるのね」
そう言ったモルガーナは、オリジナルコアを愛おしそうに撫でる。
「まだもう少し時間があるでしょう。けれど、早く決着をつけなくては……」
独り言を漏らしたモルガーナは、オリジナルコアに手をかざして台の下に収納し、玄室のようなその部屋から出る。
「まだ目覚めていないとしたら、いったい誰が私の計画に介入しているというのかしら……」
目を細め、顎に手を当てて考え込むモルガーナ。
入り口だった壁から裂け目が見えなくなったのを確認してから、彼女は広場の出口に向かって歩き始めた。
遠退いていた足音も消えた。
灯りのなくなった玄室の中は、完全な闇。
しかし光のないその場所に、光が漏れ出てきた。
隙間のないはずの台から漏れ出る、真っ白な光。
オリジナルコアが発した光。
そして、光とともに声が溢れた。
「ふふふっ。もうすぐよ、もうすぐなのよ」
姿なき者の声は、少女のような若々しさと、楽しげな色を乗せ、玄室の中に響く。
「もうすぐ終わりなのでしょう? だったら、もっと楽しくしましょう。もっと、もっと!」
狂気にも似た激しさを持つ声は、誰ひとりいないその場所で言葉を紡ぐ。
「ねぇ、魔女。貴女も見ているだけではつまらないでしょう? だから貴女も、貴女の戦いをしてちょうだい。必死に、必死に戦ってちょうだい!!」
聞く者のいない場所で言い、光とともに漏れ出る声は、ひたすらに笑っていた。
「撫子(ラバーズピンク)の憂い」 了
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました
フルーツパフェ
大衆娯楽
とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。
曰く、全校生徒はパンツを履くこと。
生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?
史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。



幼なじみとセックスごっこを始めて、10年がたった。
スタジオ.T
青春
幼なじみの鞠川春姫(まりかわはるひめ)は、学校内でも屈指の美少女だ。
そんな春姫と俺は、毎週水曜日にセックスごっこをする約束をしている。
ゆるいイチャラブ、そしてエッチなラブストーリー。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

GAME CHANGER 日本帝国1945からの逆襲
俊也
歴史・時代
時は1945年3月、敗色濃厚の日本軍。
今まさに沖縄に侵攻せんとする圧倒的戦力のアメリカ陸海軍を前に、日本の指導者達は若者達による航空機の自爆攻撃…特攻 で事態を打開しようとしていた。
「バカかお前ら、本当に戦争に勝つ気があるのか!?」
その男はただの学徒兵にも関わらず、平然とそう言い放ち特攻出撃を拒否した。
当初は困惑し怒り狂う日本海軍上層部であったが…!?
姉妹作「新訳 零戦戦記」共々宜しくお願い致します。
共に
第8回歴史時代小説参加しました!

【R18】俺は変身ヒーローが好きだが、なったのは同級生の女子でした。一方の俺は悪の組織に捕らえられマッドサイエンティストにされた
瀬緋 令祖灼
SF
変身ヒーロー好きの男子高校生山田大輝は、普通の学生生活を送っていたが、気が晴れない。
この町には侵略を企む悪の組織がいて、変身ヒーローがいる。
しかし、ヒーローは自分ではなく、同級生の知っている女子、小川優子だった。
しかも、悪の組織に大輝は捕まり、人質となりレッドである優子は陵辱を受けてしまう。大輝は振り切って助けようとするが、怪人に致命傷を負わされた。
救急搬送で病院に送られ命は助かったが、病院は悪の組織のアジトの偽装。
地下にある秘密研究所で大輝は改造されてマッドサイエンティストにされてしまう。
そんな時、変身ヒーローをしている彼女、小川優子がやって来てしまった。
変身ヒーローの少女とマッドサイエンティストの少年のR18小説
実験的に画像生成AIのイラストを使っています。
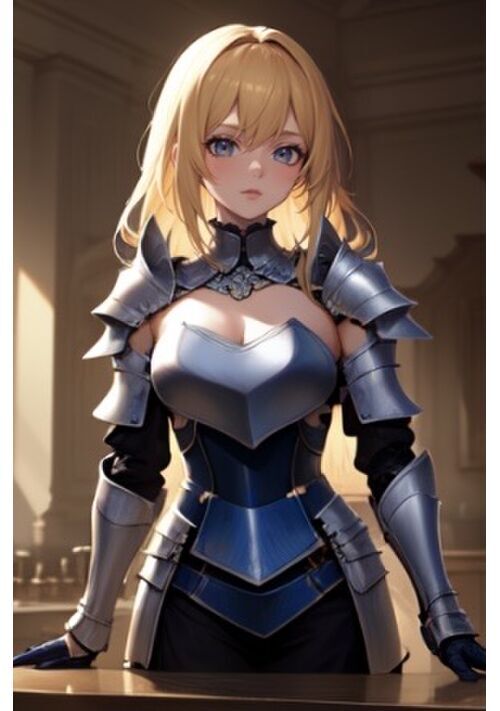
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















