64 / 150
第三部 第四章 風林火山
第三部 極炎(クリムゾン)の怒り 第四章 2
しおりを挟む* 2 *
「やっぱりてめぇか」
芳野さんのエスコートでダンスホールに姿を見せた猛臣は、僕を睨みつけて開口一番そう言った。
歯を剥き出しにして怒りを露わにしてくる彼に、夏姫が身体を寄せてくるけど、大丈夫だと声に出さない言葉を視線に籠めて目配せをし、僕は対戦相手に向き直った。
平泉夫人が対戦として設定した日曜の午後、僕は夏姫と灯理、それから近藤とともに、屋敷を訪れている。
これから始まる戦いのためだろう、ダンスホールには分厚いマットが敷き詰められ、壁沿いに置かれたソファのところにいる僕たちの他に、少し離れたところの丸テーブルでは平泉夫人がお茶を飲みながら微笑んでいた。
「本当に、何てことをしてくれたんですか、夫人。俺様がせっかく話を進めていたというのに」
「そもそも事件そのものがおかしい状況だったでしょう? 貴方が介入しているのは気づいていたけれど、私の意図に添った結果になったのは、私の力の方が勝っていたからよ。それに、貴方の望む方向とは異なっていたでしょうけれど、意図からは大幅に外れてはいないはずよ」
「ちっ」
怒りに瞳を燃え上がらせながら、微妙な感じの丁寧な言葉遣いで絡んでくる猛臣に対し、夫人は涼しい顔を向けているだけだった。
事件は結局、平泉夫人の意図通りに、謙治さんの病室で説明されたのとほぼ同じ状況に収束していた。
裏事情が表沙汰になって騒がれるようなことはなかったけど、その辺は水面下の動きが活発化してるらしい。平泉夫人側の人間は有利なカードを手に入れ、建設会社側の人間は爆弾を抱えることになったみたいで、政財界に小さな影響が出ているらしいんだけど、僕が見てる限りではよくわからない。
とにかく、まだしばらく入院しなければならないけど経過が順調な謙治さんは、少ししたら近くの総合病院に転院することが決まり、夏姫はエリキシルスフィアを売らなければならない状況が完全に消滅したことだけは確かだ。
椅子から立ち上がって部屋の中央に向かった夫人の元に、猛臣も足を踏み鳴らしながら近づいていく。夫人から目配せをされた僕たちもまた、そこに集まった。
「全員仲間ってわけか。なんでこんなことをしてる? 意味ねぇだろ。莫迦なのか?」
「僕は僕の考えでスフィアを集めてる。実際、僕の側にはソーサラーと一緒にスフィアが集まってる」
「奪い取れば後腐れねぇだろうに。ヘンな野郎だな」
「買い取って回ってる野郎に言われたくない」
近藤ほどではないけど、けっこう背の高い猛臣から強い視線が降りかかってくるけど、僕はそれに動じることなく睨み返す。
左手は、僕に力をくれるように、夏姫が握ってくれていた。
「さて。挨拶はそこまでにしましょう。今日集まってもらった理由は、もういまさら言わなくてもわかってるわね?」
「はい」
「あぁ。……理解しています」
なんでか平泉夫人に頭が上がらないらしい猛臣は、夫人の柔らかくも威圧感を覚える視線に言い直していた。
返事をした僕の他に、夏姫たちも、僕の後ろで頷いてる。
「それと、夏姫さんのエリキシルスフィアを買い取るという話、あれはなかったことにしてもらうわ」
「ふざけるな!! 一度交わした約束だ! 状況が変わったとは言え、スフィアだけは買い取らせてもらうっ」
少ししか知らないが、猛臣の性格を考えればそう言ってくるのはわかっていた。夏姫は彼に、はっきりとエリキシルスフィアを売ると宣言をしていたそうだし。
平泉夫人が大丈夫と言っていた理由は、いまこの場になってもよくわからなかった。
「夏姫さんのエリキシルスフィアを買い取る話は、なかったことにしてほいしいの。私からのお願い。貴方が私と交わした約束も、覚えているでしょう?」
「ここでそのカードを切ってくるのか!! くそっ。あんな約束、しなけりゃよかったぜ……」
片手で顔を覆い、親指と薬指でこめかみを強く押さえてる猛臣。
夫人とのやりとりがどういうことなのかはわからなかったが、猛臣は何か願いを聞くという約束でもさせられていたらしい。そんな貸しを、夫人がどうやって猛臣につくっていたのかはわからなかったが。
「もちろんそれでは収まりがつかないでしょう? だからここで、バトルをして決着をつけてもらおうと思ってね、集まってもらったのよ」
「ちっ。くそっ。わかったよ! ……わかりました。それで構いません! 夏姫のスフィアを買い取る話は白紙にします! んで、戦うのは誰なんだ?! もう面倒臭ぇから、全員相手になってやるぜっ」
「戦うのは僕だけだ」
僕たち全員を見渡して睨んでくる猛臣に、そう応えた。
「あっちがあぁ言ってるんだ、ここは全員でかかった方がいいんじゃないか? 克樹」
「ワタシも同意見です。猛臣さんが強いのはわかっていますが、全員でかかればなんとかなると思います」
「僕は、そうは思わない」
振り向いた僕は、険しい視線を向けてくる近藤と、眉根にシワを寄せている灯理に笑いかける。
「そりゃあこれまで訓練してきたから、お互いどんな風に戦うかはわかってるけど、一緒に戦う練習はしてないからね。連携が取れないなら、むしろ戦力は低下するよ」
夏姫に目を向けると、彼女は笑っていた。僕の考えを理解してるみたいに。
「それに、こいつとの決着は僕がつけたいんだ」
「いけそう?」
「うん。勝敗はどうなるかわからないけど、戦うための準備は整えてきたよ」
「ん。なら、アタシは克樹に任せる」
「克樹さんと夏姫さんがそうおっしゃるなら」
「仕方ないな。任せるよ、克樹」
「うん」
猛臣に向き直り、僕は宣言する。
「ということで、お前とは僕が戦う」
「はっ! 勇ましいな。俺様もこの前とは違うぜ」
「それは僕も同じだ」
怒りと、でも楽しげな色を浮かべてる瞳の猛臣と視線を交わし、僕はソファのある壁際へと向かう。そこに置いてあるデイパックからスマートギアを取り出して被り、アタッシェケースに手を伸ばしてドールを準備する。
『リーリエ、いけるな?』
『もっちろんっ。準備万端だよ!』
たぶんイシュタルだろう、壁に近い位置に金色の、稲穂を思わせる控えめの色合いのドールを立たせた猛臣。彼は僕に不審そうな視線を向けてくる。
「てめぇ……。嘗めてんのか? もう一体出せよ。それくらいじゃねぇと俺様とは戦えねぇぞ」
僕が足下に立たせたのは、アリシアのみ。
早速アリシアとリンクしたリーリエは、金髪をポニーテールに結ったイシュタルに笑みを向けている。
「必要ない」
「嘗めてると瞬殺するぞ」
「大丈夫だ。シンシアを出すより、アリシア一体の方が強い」
「この前は手加減してたとでも言うつもりか?」
「そうじゃないけど……。まぁ、戦えばわかるよ。そっちのドールはイシュタルって名前でいいのかな?」
「そうだよ。俺様の最強のドールだ」
どちらかというわけではなく会話が途切れ、リーリエと猛臣は互いのドールを前に歩ませる。
その様子を見つめるみんなの息を呑む音が聞こえる中、茶器を乗せているカートの下からゴングを取り出した芳野さんがそれを構える。
被ったスマートギアのディスプレイを下ろし、猛臣もヘルメット型スマートギアのバイザーを下ろし、準備は整った。
必要なアプリと、エリキシルバトルを立ち上げ、音声入力を待つウィンドウが現れたところで、僕と猛臣は同時に頷いた。
次の瞬間に鳴らされた盛大なゴングの音。
僕と猛臣は、互いに自分の願いを込めて、唱えた。
「アライズ!!」
*
バトルは静かな始まりを見た。
百二十センチとなった、水色のツインテールを肘の辺りまで垂らすアリシアと、金色のポニーテールを背の半ばまで伸ばすイシュタルは、動き出すことなく、見つめ合う。
『最初から使う?』
『いや、初めは様子を見る。たぶんウカノミタマノカミと同じようにいろいろ仕込んであると思うんだけど、何だかわからない』
『わかった』
僕の返答に、リーリエはアリシアの背に提げていた折り畳みのハルバードを取り、構えさせた。
対するイシュタルは、腰に佩いていた長剣を抜く。
アリシアはもちろん、イシュタルも他にいくつかの武器を装備してるけど、それはまだ使わない。
体型からしてスピード寄りのバランスタイプだと思われるイシュタル。
ほぼ全身をハードーアーマーで覆うイシュタルは、とくに肩と腰、脚のアーマーが重厚だ。それに加えて、肩と腕には、爪か牙のように見える刃状の装飾が取りつけられていた。
――ウカノミタマノカミのことを考えれば、あれはただの飾りじゃないよな。
そうは思っても、戦ってみなければわかるもんじゃない。
どう攻めるべきかを考えてるとき、猛臣が先に動いた。
「何睨み合ってんだっ。さっさと終わらせちまうぜ!」
言いながら猛臣は、イシュタルの体勢を低くし、突撃の構えを取った。
そして、叫んだ。
「ライトニングシフト!」
その瞬間、イシュタルは金色の光となった。
「電光石火!」
かろうじて反応し、僕は必殺技を発動させる。
金の光となって突進してきたイシュタルを、リーリエはアリシアを右に飛び退って回避させる。
「その程度の動き、見えてるって言ってんだろ!」
マットに脚を押しつけてブレーキをかけたイシュタルが、回避したアリシアに追いすがって長剣を振るう。
『甘いよっ』
僕にだけ聞こえる声で言ったリーリエは、横薙ぎに振るわれた長剣をハルバードで器用に絡め取り、マットに押しつける。
剣の腹を足で踏んづけて固定したアリシアは、ハルバードを突き出して反撃に出た。
「ちっ。見切りのいい」
僕が舌打ちをしてしまうほどに、ためらいもなく長剣から手を離したイシュタルは、腰から幅広の剣を二本抜いてハルバードを受け止めていた。
『押し切る! 疾風怒濤!!』
『うんっ!』
距離を取ろうと後ろに下がったイシュタルを追いかけ、アリシアは前に出てハルバードの尖った先端を突き込む。
必殺技、リミットオーバーセットによって通常を遥かに超える筋力と速さを手に入れたアリシアは、二本の剣では防ぎきれないほどの速度でハルバードの穂先を連続して突き出した。
「うおぉぉぉっ! サンダーストーム!!」
それがたぶん猛臣の必殺技の名前なんだろう。
ハルバードの穂先がアーマーをかすめるのと同時に彼は叫び、イシュタルの動きが変わった。
本物の刃物と同じ銀の光を放つハルバードの穂先を、光る筋となった幅広剣の軌道が次々と打ち落としていく。
それどころか、まさに疾風怒濤の攻撃の合間を縫って、斧槍と剣のリーチの差さえ埋め、反撃までしてきた。
――なんて奴だ!
金属と金属のぶつかり合う音が、音楽のように連続して鳴り響く。
「うっ、らーーーっ!」
『一端下がれ、リーリエ!』
交差した幅広剣にハルバードを挟まれ、穂先を斬り落とされたのを見て、僕はリーリエにイシュタルから離れるよう指示していた。
距離を取り、肩の後ろに手を伸ばして長刀を抜き放ったアリシアは、イシュタルと見つめ合う。
『この人、やっぱり本当に強いよ』
『あぁ。そうだな』
『――ゴメンね、おにぃちゃん』
『何がだ?』
『あたしいま、すっごく楽しい』
『……そうだな』
言葉通りに戦いを楽しんでるリーリエは、アリシアに笑みを零れさせる。
対するイシュタルも、可動型フェイスが笑みに染まり、その後ろに立つ猛臣もまた、ヘルメットに隠されていない唇の端をつり上げて笑っていた。
――確かに、強い。それに、楽しい。
心の中でリーリエに同意しながら、僕は視界の端に表示したアリシアの目を通して上がってくるデータを見る。
使っているパーツの予想は、ほとんどが不明。
市販されているどのパーツにも該当しないと思われる高い性能の人工筋が使われているようだった。
けれど、必殺技による性能上昇率はアリシアの方が上。
エリキシルドールの性能は、ほぼ拮抗していた。
経験は未熟ながら、人間の反応速度を超えるリーリエを相手に、すべての動作を先読みして動く平泉夫人とも違い、猛臣は目で見てから反応しているようだった。
悔しいけど、ソーサラーとしての強さは猛臣に軍配が上がっていた。
『ねぇ、おにぃちゃん。お願いがあるの』
『なんだ? リーリエ』
両手で持った長刀を肩の上で構えさせてるリーリエが、珍しく僕にお願いをしてくる。
それは、内容が予想できるお願いだった。
『あたし、もう少しだけ、あの子と戦っていたい』
『いいよ、もう少しだけならな。でも「風林火山」を使うタイミングは、外すなよ』
『うんっ、わかってる』
ちらりとアリシアで視線を送ってきたリーリエに、僕は頷きを返した。
『行けっ、リーリエ!』
『いーーくっ、よーーっ! イシュタル!!』
そんな声を上げながら、リーリエはアリシアをイシュタルに向けて突撃させた。
――本当にやるじゃねぇか、あいつ!
先ほどハルバードのときに見せた高速の突きに比べれば遅い、長刀による突きを主体にしたアリシアからの攻撃を、悠々とイシュタルの二本の幅広剣で凌ぎながら、猛臣は口元に笑みが浮かぶのを止められなかった。
前回の戦闘では、アリシアとシンシアの二体でそこそこの強さだった。
アリシア一体ではすぐに決着がついてしまうだろうと思っていたのに、その予想は裏切られていた。
剣の軌道を読んで、防御の薄い場所を狙い澄まして突き出される長刀に、猛臣は奥歯を噛みしめる。
彼の視界には、イシュタルの視界と同時に、エリキシルドールの状態を示すパラーメーターウィンドウや、解析で判明してきているアリシアに関する情報が表示されていた。
さらに、視界の下の方には、色分けされたいくつものボタンがある。
裁ききれないことはないが、アーマーをかすめるほどに鋭いアリシアの攻撃に苛立ちを感じ始めた猛臣は、八個のポインタのうちひとつを、ボタンのひとつの上に移動させた。
突きと突きの隙間に、大きくマットを蹴ってイシュタルをアリシアから引き離した彼は、準備したボタンのひとつを押しながら叫んだ。
「サンダーサイクロン!!」
イシュタルは両腕を広げ、身体を回転させながらアリシアへと飛ぶ。
右の幅広剣を立てた長刀で受け止められるも、無視して振り抜き、背を見せながら回転して左の幅広剣を叩きつける。
人工筋のリミットを外し、躱されてもなお高速に回転しながら攻撃を続ける様子は、さながら竜巻。
「疾風迅雷!!」
猛臣が叫び、長刀を捨て短刀二本でイシュタルの攻撃を防いでいたアリシアが素早く後退する。
追いすがって攻撃を仕掛けるものの、激しい動作と高い電圧で温度が上昇していた人工筋のステータス表示が悲鳴のような警告音を鳴らし始めた。
――ちっ。仕留めきれないか。
サンダーサイクロンによる攻撃はアリシアの水色のハードーアーマーを幾度もかすめていたが、防御を切り崩すことはできず、致命的なダメージを与えるには至らなかった。
ドールの性能は第五世代バトルピクシーとしては並よりも上。ソーサラーの能力はスフィアカップ全国大会ベスト八レベル。
何より厄介なのは、声とともに使用している技だった。
――性能上昇率も精度もこっちより上か。
克樹が通常のピクシードール用人工筋の規定電圧を超える、リミットーバーセットを使っているのは、前回の戦いでもわかっていた。
スフィアカップなどのレギュレーションがしっかりしている公式戦では使用できないが、リミットオーバーセットは人工筋の使用方法としてはよく知られたもの。
エリキシルバトルに参加するに当たって、猛臣は規定外の動作であるそれを使用できるよう、ドールのコントロールアプリのアドオンモジュールをつくり上げた。
発熱などにより長時間使うのが難しいそれを、猛臣は特定の動作に分けてボタンによる制御を行い、細かい状況の変化については自身のフルコントロールで対応している。補い切れない部分は、特別製のアドオンにより、事前に打ち込んだ方針に従って行動するセミコントロールで補っていた。
フルコントロールとセミコントロールを組み合わせた、セミオートソーサリーと名づけたコントロールこそが、イシュタルやウカノミタマノカミの強さのひとつだった。
猛臣がスキルと呼んでいるリミットオーバーセットは、ある程度大雑把な動作になってしまうのは否めなかったが、克樹の使うスキルは特定の動作に制限されず、性能の上昇率もイシュタルが使うものに比べて高いと計測されていた。
――あいつはいったいどうやってあそこまで細かい制御を行ってるんだ? あいつもセミオートで戦ってるのか?
逆手に持った短刀で突撃してきたアリシア。
それに応じて短剣を二本抜き、猛臣は超接近距離でのエッジバトルを開始する。
スキルを使わずとも人の目では捉えきるのが難しい攻撃を、猛臣は頭部以外の身体の各部に取りつけた視覚センサーをオンにして、スマートギアの視界に小窓で表示して補い、裁く。
――こいつがこんなに強いソーサラーだったとはなっ!
人工筋だけでなく、自身の身体すら熱くなってくるのを感じるバトルを続けながら、猛臣は楽しくて仕方がなかった。
関東にいるソーサラーで一番警戒すべきは、近藤誠だと思っていた。
全国大会に出場している近藤がエリキシルバトルの参加者であることは、通り魔事件の顛末を見れば明かだった。逮捕されたことでスフィアを奪われている可能性も考えられたが、まだ参加者だった彼の強さは、拍子抜けするほどにたいしたことがなかった。
それよりもイレギュラーな参加者であった中里灯理の方が脅威を感じたが、克樹についてはたいしたことがないだろうと思っていた。
地方大会で優勝しながらも全国大会への出場を辞退し、ソーサラーであった百合乃を失っている克樹。オーナーに過ぎない克樹がこれほどまでに強いなどとは、予想もしていなかった。
――何か裏がありそうではあるがなっ。
映像で見たことがある、亡くなった百合乃とほとんど同じ繊細なドールコントロールと、スキルの細やかな調整を同時に行っている様子なのには、何か裏がありそうだと感じていた。
――でも、そんなことはどうでもいい!
心の中で叫んだ猛臣は、アリシアを蹴り飛ばして距離を取り、短剣を捨てた。
「そろそろ本気を出させてもらうぞ、克樹!」
超硬質合金で覆われた手を顔の前で握りしめたイシュタル。
そう克樹に宣言した猛臣は、視界の下に並んだボタンのひとつを押す。
「ライトニングドライブ!」
全身の人工筋の電圧を一割上げる設定を行うそれは、使っている間イシュタルの動作速度を上昇させるスキル。
より高速になるイシュタルの動きを制御するのは難しくなるが、エリキシルバトルに勝ち残りために、猛臣は訓練を続けてきた。
「僕もそろそろ本気を出す。来いっ、猛臣!」
「覚悟しな! 克樹!!」
短刀を捨て、手甲に接続されたナックルガードを構えるアリシアに、猛臣はイシュタルを走らせた。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました
フルーツパフェ
大衆娯楽
とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。
曰く、全校生徒はパンツを履くこと。
生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?
史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。



幼なじみとセックスごっこを始めて、10年がたった。
スタジオ.T
青春
幼なじみの鞠川春姫(まりかわはるひめ)は、学校内でも屈指の美少女だ。
そんな春姫と俺は、毎週水曜日にセックスごっこをする約束をしている。
ゆるいイチャラブ、そしてエッチなラブストーリー。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

GAME CHANGER 日本帝国1945からの逆襲
俊也
歴史・時代
時は1945年3月、敗色濃厚の日本軍。
今まさに沖縄に侵攻せんとする圧倒的戦力のアメリカ陸海軍を前に、日本の指導者達は若者達による航空機の自爆攻撃…特攻 で事態を打開しようとしていた。
「バカかお前ら、本当に戦争に勝つ気があるのか!?」
その男はただの学徒兵にも関わらず、平然とそう言い放ち特攻出撃を拒否した。
当初は困惑し怒り狂う日本海軍上層部であったが…!?
姉妹作「新訳 零戦戦記」共々宜しくお願い致します。
共に
第8回歴史時代小説参加しました!

【R18】俺は変身ヒーローが好きだが、なったのは同級生の女子でした。一方の俺は悪の組織に捕らえられマッドサイエンティストにされた
瀬緋 令祖灼
SF
変身ヒーロー好きの男子高校生山田大輝は、普通の学生生活を送っていたが、気が晴れない。
この町には侵略を企む悪の組織がいて、変身ヒーローがいる。
しかし、ヒーローは自分ではなく、同級生の知っている女子、小川優子だった。
しかも、悪の組織に大輝は捕まり、人質となりレッドである優子は陵辱を受けてしまう。大輝は振り切って助けようとするが、怪人に致命傷を負わされた。
救急搬送で病院に送られ命は助かったが、病院は悪の組織のアジトの偽装。
地下にある秘密研究所で大輝は改造されてマッドサイエンティストにされてしまう。
そんな時、変身ヒーローをしている彼女、小川優子がやって来てしまった。
変身ヒーローの少女とマッドサイエンティストの少年のR18小説
実験的に画像生成AIのイラストを使っています。
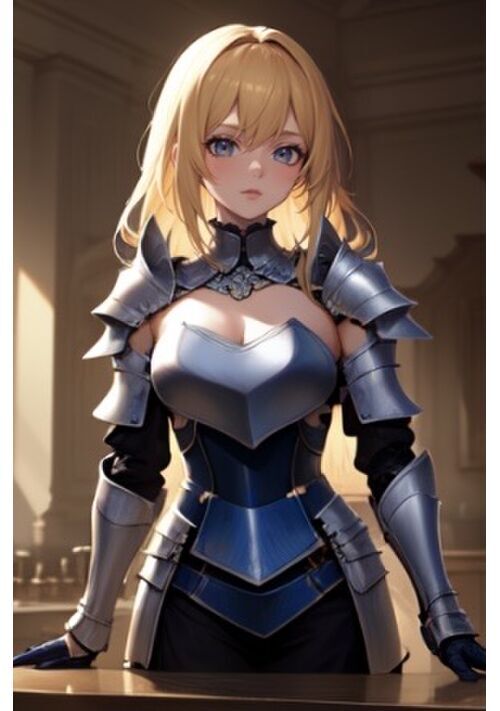
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















