57 / 150
第三部 第二章 クリムゾン・エッジ
第三部 極炎(クリムゾン)の怒り 第二章 4
しおりを挟む
* 4 *
思っていた通りの時間に人気のない教室に入ってきたのは、遠坂。
「遠坂。ちょっと訊きたいことがある」
「え? 克樹? どうしたの? こんな早くに」
鞄から教材すら取り出さずに待っていた僕は、席から立ち上がって教団側の入り口で目を見開いてる遠坂の側に駆け寄っていく。
彼女が今日日直なのは、授業用アプリの予定表で確認済み。
他の奴らが教室にやってくる前に来て、僕は彼女を待ち受けていた。
「ちょ。ちょっとっ。何なの? 腕引っ張らないでよ!」
「なんだ? 音山。遠坂さんに告白でもするのか?」
「あー。まぁそんな感じ。他の奴らには秘密にしておいてくれよ」
少し遅れてやってきた日直の相方の男子に、いつもなら軽口で返すところを余裕がないから適当に返事して、僕は遠坂の腕を引っ張って教室を出ようとする。
「何なのよっ、克樹!」
「だからちょっと話があるんだって。どこか、話せるところで……」
「遠坂さんも察してやれよ。浜咲さんのことだろ? 今週に入ってから来てないじゃん」
「あー」
二年になってから同じクラスになった名前も憶えてない男子の意外な支援に、遠坂は納得した顔になるが、すぐに表情を曇らせた。
昨日、猛臣から逃げてきた灯理と近藤が帰った後にもブリュンヒルデの反応を確認してみたけど、まだ夏姫のアパートにあることは確認できた。
でもいつあいつが夏姫に接触しないとも限らない。
一刻も早く彼女の状況を確認しておく必要があった。
「朝の仕事はやっとくから、午後の分は頼むわ」
「……わかった。ありがと。克樹、こっち来て」
教室から引っ張り出そうとしていた僕と立場が逆転して、遠坂が僕の手首をつかんで廊下をずんずんと歩いていく。
連れてこられたのは校舎とは別棟の、部室棟。
主に運動部が使ってる隅っこの部屋の前に立ち、鍵を携帯端末で解除した遠坂は、扉を開けて中を確認する。
「ちょ、ちょっと待ってて」
「わかった」
自分が入る分の隙間を空けて中に滑り込んだ遠坂は、部室内で何かを仕舞ってるらしい。ロッカーを開けたり閉めたりと、ドタバタした音が聞こえてくる。
「うん。大丈夫。入って」
まだ運動部の朝練が終わるには早い時間、人気をあんまり感じない廊下に立ってた僕は、その声に陸上部の部室に入った。
中は別にたいしたことはない。陸上部でしか使わない用具が置かれていたり、窓のない両方の壁にロッカーが並んでいたり、校庭に繋がる扉がある程度の、普通の部室だ。
ただ、弱小で主に女子部員で構成され、男子は他の部の更衣室を間借りしてる状況の陸上部の部室は、土や汗の臭いよりも、制汗スプレーとか化粧だとかの、女の子の匂いが強かった。
思えばあんまり化粧をしてるのを見たことがない遠坂は、考え込むように顔をうつむかせながら、部屋の真ん中に置かれたベンチに座った。少し間を開けて僕も腰掛ける。
こんなところでふたりきりのところを誰かに見られたらと思うけど、これから徐々に増えてくる他の奴らの目を気にせず話せるこの場所はありがたい。ちょっと、女の子の匂いで酔いそうではあるけど。
「夏姫から連絡はないの?」
「ない」
問うより先に口を開いた遠坂は僕の返事に、目を細めながらうつむいた。
「夏姫に何があったんだ? 昨日から何か言いたいことがありそうにしてたのはわかってる。あいつのことで、何か知ってることがあるんだろ?」
「それは、その……」
「どうしたんだよ」
いつもなら思うよりも先に口から言葉が出てる遠坂は、胸の前で拳を握りしめてためらうように何も言わない。
コンクリートの床に目を向けてる彼女の肩に手を伸ばし、無理矢理僕の方を向かせた。
「話してくれ、遠坂」
「夏姫から、克樹にだけは絶対に言わないで、って言われてるの」
「何だよ、それ。あいつに何があったのか? 家族の事情って、あいつのお父さんに何かあったとか?」
「知ってるんだ? 夏姫の家のこととか」
「少しだけだけどね。そんなに詳しいわけじゃない。あんまり話したくないみたいだし」
「うん。そうなんだよね……」
少し泣きそうに目を潤ませてる遠坂の様子に、僕の問いが間違っていないことを確認する。
でももし夏姫に何かしてやるとしても、詳しい話を聞かないとどうにもならない。あいつのところに駆けつけてやるべきなのかどうかもわからない。
「ねぇ、克樹。克樹にとって、夏姫って……、どういう相手なの?」
「い、いきなり何言ってるんだよっ」
突然何を言い始めたのかと、遠坂の問いに僕は混乱してベンチから滑り落ちそうになってしまっていた。
「克樹ってさ、責任感が強いって言うか、お節介焼きで、泣いてる人のことを放っておけない質だよね?」
「そっ、そんなわけないだろっ。僕は……、その、女の子が好きで、エッチなのも好きで、責任とか、そういうのは――」
「嘘吐き」
いたたまれなくて立ち上がって逃げようとする僕のシャツの胸元をつかみ、遠坂が顔を近づけてくる。
潤んでいても真っ直ぐに見つめてくる瞳。
遠坂の瞳の中に、揺らぎながらも僕の顔が映ってるのが見えた。
「あんたとのつき合い、もうどれくらいになると思ってるの? 男の子だってのは本当だし、わかってるけど、でもそうじゃないでしょ? あんたって。百合乃ちゃんがいたからってのはあっただろうけど、あんたがワタシのことどれだけ助けてくれたのか、わかってるよ。ワタシや百合乃ちゃんが忙しくて手が離せないとき、あんたが手伝ってくれたの、知ってるよ。いつも不器用だったけどね……」
懐かしむようにして視線を下げていた遠坂が顔を上げ、睨むほどに強い視線を僕に向けてくる。
「あんたは昔からそう。面倒臭そうにしてても、結局ちゃんとしてる。そのことは、他の誰よりも、夏姫なんかよりも、ワタシが知ってるんだから」
「……」
あの頃、僕は百合乃を通してしか遠坂とつき合いがなかった。遠坂とだけ話すようになったのは、百合乃が死んだ後からだった。
百合乃が死に、荒れてた時期の僕にめげずに話しかけてくる遠坂のことは鬱陶しかったけど、感謝もしてる。僕がいまの僕になれたのは、リーリエがいてくれたからと言うのが一番大きいと思うけど、遠坂がいてくれなければリーリエを生み出すこともなく、荒れ続けていたかもしれない、とも思う。
「何だよお前。僕のファンかよ。なんでそんなに僕のこと見てるんだよ」
気恥ずかしくなって、僕は誤魔化すようにそんなことを口にしてしまっていた。
「そうだよ、ファンだよ。ワタシはあんたのファンなのっ。いつも元気で優しい百合乃ちゃんのことが好きだったよ。でもね、克樹。ワタシはその百合乃ちゃんのお兄ちゃんをしっかりやってる克樹のこと、見てたよ。だからワタシは、あんたのファンなんだよ!」
「な、何を言ってんだよっ」
言ってしまった僕の方が恥ずかしくなるようなことを言い返されて、僕は顔が熱くなるのも感じていた。
でも遠坂は、そんな僕の顔を見ながら、泣きそうな顔をしている。
「夏姫のこと、話した方がいいんじゃないかと思ってる。口止めされてるけど、克樹には話しておいた方がいいと思う。でもね、克樹。夏姫のこと助けようとしたら。克樹はあの子のいろんなことを背負わないといけないと思う」
「……そんな、状況なのか?」
「うん。そういう問題なの。克樹はたぶん、聞いちゃったら放っておけない。そういう奴だもん、克樹って」
泣きそうな顔で、遠坂は笑う。
かなり重い問題だろうことは予想してた。夏姫がまったく連絡をよこさないくらいだ、けっこう酷い状況なんだろうとは思ってた。
それに遠坂の言うこともわかる。
僕は何か問題がある人を見かけたら、放っておけない。無理や無茶はできないし、自分のできる範囲でしかやらないけど、性分なのか、完全には放っておくことなんてできない。
遠坂の指摘は正しい。それは僕自身がよく知ってる。
「中途半端に助けようとなんてしたら、たぶん夏姫が迷惑する。克樹も大変なことになる。だから教えて。克樹にとって、夏姫って、どんな人なの?」
「僕にとって夏姫は……」
微笑みながら問うてくる遠坂に、僕は自分に答えを問うていた。
これまで見てきた夏姫の顔が浮かぶ。彼女の言葉を思い出す。
そして一番最初の、夏姫の存在を初めて知ったときの想いが、いまは僕の中で育って大きくなっていることを意識する。
「僕にとって夏姫は――」
泣きそうな顔で笑ってる遠坂に、僕は僕の想いを告げた。
*
「てめぇふざけんなっ。ありゃあいったいなんだ?!」
かかってきた通話着信の名前を見て、猛臣は応答ボタンを押すと同時に叫ぶように言葉を放った。
『あんまりな挨拶ね。いきなり何なのかしら?』
「何なのも何もねぇ。いったい何なんだっ、あの中里灯理って奴は!」
『あぁ、なるほど。彼女と接触したのね』
猛臣の怒気にも怯むことなく、電話の相手は涼やかな声で応答する。
連泊しているホテルの部屋のテーブルに転がっているスレート端末には、ほんの少し前に届いた中里灯理の情報が表示されていた。
ソファに座り、テーブルに脚を投げ出して携帯端末に耳を当てている猛臣の顔は、怒りに赤く染まっている。
「聞いてねぇぞ、モルガーナ! スフィアカップに参加してない奴がなんでエリキシルスフィアを持ってやがるっ。いったいどういうことなんだ!!」
SR社の研究所に出入りしているという仕事の関係上、何度か直接話し、メールなどで連絡を取ることもあるモルガーナ。
エリキシルバトルの主催者が彼女であることは、少ない情報を頼りに調べていっても、猛臣が気づくまでにはさほど時間は必要なかった。
五年ほどの間にロボット業界を席巻したと言っても過言ではないスフィアドール。その原動力となり、製造方法は不明で、同程度のものを再現することもできないスフィア。
その一番重要な部分であるスフィアコアは、多くの謎に包まれている。
エリキシルバトルに参加する前でも、SR社の動きやロボット業界の動向を探っていれば、誰かひとりの人間の意図に左右されていることは感じ取ることができる。それを槙島という家の力を使って調べていけば、モルガーナにたどり着くことができた。
しかし彼女の存在に気づくときには、彼女の持つ影響力の強さ、そしてその範囲の広さに気づくことになる。
いまこの世界にモルガーナは不可欠なほどに重要であり、ヘタに触れば超大国であっても揺るがしかねない。それほどの力をはっきりと見出すことができるわけではなかったが、そう思えるほどの雰囲気を、猛臣は感じていた。
そして巧妙に存在を隠されつつも、たどり着く者にはそうしたことに気がつくよう仕組まれているようだった。
猛臣の知る限り、エリキシルバトルなどというものを開催可能な力と、現実離れした現象を起こしうる存在は、モルガーナしかいなかった。
そのことを指摘した猛臣に、モルガーナはあっさり自分が主催者であることを認めた。それからは、仕事以外のことでも連絡を取る機会が生まれていた。
『どうなっていると言われても、彼女もまたエリキシルバトルの参加者というだけの話よ。エイナから聞いているでしょう? 参加資格があるのは特別なスフィアを持つ者。決してスフィアカップの地方大会の優勝者と準優勝者に限定はしていないわ』
「ふざけんじゃねぇ! だったら他に中里灯理みたいな奴が何人いるのか教えやがれ!」
『それは無理な話ね。貴方にだけ情報を与えるなんて優遇はできないのよ、猛臣君。スフィアの買い取って集めることを認めただけでも、貴方のことは充分優遇していると思うのだけど?』
「……てめぇ」
映像のない通話オンリーの携帯端末の表示を睨みつけ、目の前にいたら殴りたい気持ちを舌打ちして堪える。
エリキシルバトルに参加し、自分と同じ特別なスフィアを持つ相手の中から参加者を捜し始めた猛臣は、エリキシルスフィアを買い取るという方法によって集めることにした。
猛臣にとってピクシードール、エリキシルドールで戦うこともバトルならば、資金という力を使って行うものも、戦いのひとつであったから。その方法を採ることにためらいはなかった。
それにストップをかけるべく連絡をしてきたのは、モルガーナ。
一度は禁止された買い取りはしかし、中盤戦に入ってから解禁されていた。
必ず連絡が取れるわけではなかったが、買い取りが許可されたことも、主催者と直接連絡が取れることも確かに優遇ではあったが、イレギュラーな参加者がいることに納得ができるわけではなかった。
『それで、連絡した用件だけれど、貴方が会社に手配の依頼してきた部品の都合がついたわ。さっきの件のお詫びというわけではないけれど、最優先で出荷するよう指示しておいたから』
「あぁ、もう届いてるよ」
ちらりと簡易デスクに目を走らせた猛臣。
そこには朝に届いた宅配便のダンボールが置かれている。まだ依頼したすべてのパーツが揃ったわけではないが、最低限のものは届いていた。
『それともうひとつ、貴方が興味を持ちそうな情報が入ってきたから、まとめさせておいたわ。そろそろ届いてるんじゃないかしら?』
「情報?」
言ってる間にスレート端末がメールの着信を告げた。
携帯端末を左手で耳に当てたまま、伸ばした右手でテーブルの上のスレート端末を操作し、メールを表示する。
「……なるほど。これはまた」
『満足していただけたかしら?』
「あぁ、充分だ。ありがとよ」
『これからも良い戦いを期待しているわ』
それだけ言って、モルガーナからの通話が切断された。
携帯端末をテーブルに置いた猛臣は、スレート端末を手に取り、情報を眺めていく。
その口元には、不適な笑みが浮かんでいた。
思っていた通りの時間に人気のない教室に入ってきたのは、遠坂。
「遠坂。ちょっと訊きたいことがある」
「え? 克樹? どうしたの? こんな早くに」
鞄から教材すら取り出さずに待っていた僕は、席から立ち上がって教団側の入り口で目を見開いてる遠坂の側に駆け寄っていく。
彼女が今日日直なのは、授業用アプリの予定表で確認済み。
他の奴らが教室にやってくる前に来て、僕は彼女を待ち受けていた。
「ちょ。ちょっとっ。何なの? 腕引っ張らないでよ!」
「なんだ? 音山。遠坂さんに告白でもするのか?」
「あー。まぁそんな感じ。他の奴らには秘密にしておいてくれよ」
少し遅れてやってきた日直の相方の男子に、いつもなら軽口で返すところを余裕がないから適当に返事して、僕は遠坂の腕を引っ張って教室を出ようとする。
「何なのよっ、克樹!」
「だからちょっと話があるんだって。どこか、話せるところで……」
「遠坂さんも察してやれよ。浜咲さんのことだろ? 今週に入ってから来てないじゃん」
「あー」
二年になってから同じクラスになった名前も憶えてない男子の意外な支援に、遠坂は納得した顔になるが、すぐに表情を曇らせた。
昨日、猛臣から逃げてきた灯理と近藤が帰った後にもブリュンヒルデの反応を確認してみたけど、まだ夏姫のアパートにあることは確認できた。
でもいつあいつが夏姫に接触しないとも限らない。
一刻も早く彼女の状況を確認しておく必要があった。
「朝の仕事はやっとくから、午後の分は頼むわ」
「……わかった。ありがと。克樹、こっち来て」
教室から引っ張り出そうとしていた僕と立場が逆転して、遠坂が僕の手首をつかんで廊下をずんずんと歩いていく。
連れてこられたのは校舎とは別棟の、部室棟。
主に運動部が使ってる隅っこの部屋の前に立ち、鍵を携帯端末で解除した遠坂は、扉を開けて中を確認する。
「ちょ、ちょっと待ってて」
「わかった」
自分が入る分の隙間を空けて中に滑り込んだ遠坂は、部室内で何かを仕舞ってるらしい。ロッカーを開けたり閉めたりと、ドタバタした音が聞こえてくる。
「うん。大丈夫。入って」
まだ運動部の朝練が終わるには早い時間、人気をあんまり感じない廊下に立ってた僕は、その声に陸上部の部室に入った。
中は別にたいしたことはない。陸上部でしか使わない用具が置かれていたり、窓のない両方の壁にロッカーが並んでいたり、校庭に繋がる扉がある程度の、普通の部室だ。
ただ、弱小で主に女子部員で構成され、男子は他の部の更衣室を間借りしてる状況の陸上部の部室は、土や汗の臭いよりも、制汗スプレーとか化粧だとかの、女の子の匂いが強かった。
思えばあんまり化粧をしてるのを見たことがない遠坂は、考え込むように顔をうつむかせながら、部屋の真ん中に置かれたベンチに座った。少し間を開けて僕も腰掛ける。
こんなところでふたりきりのところを誰かに見られたらと思うけど、これから徐々に増えてくる他の奴らの目を気にせず話せるこの場所はありがたい。ちょっと、女の子の匂いで酔いそうではあるけど。
「夏姫から連絡はないの?」
「ない」
問うより先に口を開いた遠坂は僕の返事に、目を細めながらうつむいた。
「夏姫に何があったんだ? 昨日から何か言いたいことがありそうにしてたのはわかってる。あいつのことで、何か知ってることがあるんだろ?」
「それは、その……」
「どうしたんだよ」
いつもなら思うよりも先に口から言葉が出てる遠坂は、胸の前で拳を握りしめてためらうように何も言わない。
コンクリートの床に目を向けてる彼女の肩に手を伸ばし、無理矢理僕の方を向かせた。
「話してくれ、遠坂」
「夏姫から、克樹にだけは絶対に言わないで、って言われてるの」
「何だよ、それ。あいつに何があったのか? 家族の事情って、あいつのお父さんに何かあったとか?」
「知ってるんだ? 夏姫の家のこととか」
「少しだけだけどね。そんなに詳しいわけじゃない。あんまり話したくないみたいだし」
「うん。そうなんだよね……」
少し泣きそうに目を潤ませてる遠坂の様子に、僕の問いが間違っていないことを確認する。
でももし夏姫に何かしてやるとしても、詳しい話を聞かないとどうにもならない。あいつのところに駆けつけてやるべきなのかどうかもわからない。
「ねぇ、克樹。克樹にとって、夏姫って……、どういう相手なの?」
「い、いきなり何言ってるんだよっ」
突然何を言い始めたのかと、遠坂の問いに僕は混乱してベンチから滑り落ちそうになってしまっていた。
「克樹ってさ、責任感が強いって言うか、お節介焼きで、泣いてる人のことを放っておけない質だよね?」
「そっ、そんなわけないだろっ。僕は……、その、女の子が好きで、エッチなのも好きで、責任とか、そういうのは――」
「嘘吐き」
いたたまれなくて立ち上がって逃げようとする僕のシャツの胸元をつかみ、遠坂が顔を近づけてくる。
潤んでいても真っ直ぐに見つめてくる瞳。
遠坂の瞳の中に、揺らぎながらも僕の顔が映ってるのが見えた。
「あんたとのつき合い、もうどれくらいになると思ってるの? 男の子だってのは本当だし、わかってるけど、でもそうじゃないでしょ? あんたって。百合乃ちゃんがいたからってのはあっただろうけど、あんたがワタシのことどれだけ助けてくれたのか、わかってるよ。ワタシや百合乃ちゃんが忙しくて手が離せないとき、あんたが手伝ってくれたの、知ってるよ。いつも不器用だったけどね……」
懐かしむようにして視線を下げていた遠坂が顔を上げ、睨むほどに強い視線を僕に向けてくる。
「あんたは昔からそう。面倒臭そうにしてても、結局ちゃんとしてる。そのことは、他の誰よりも、夏姫なんかよりも、ワタシが知ってるんだから」
「……」
あの頃、僕は百合乃を通してしか遠坂とつき合いがなかった。遠坂とだけ話すようになったのは、百合乃が死んだ後からだった。
百合乃が死に、荒れてた時期の僕にめげずに話しかけてくる遠坂のことは鬱陶しかったけど、感謝もしてる。僕がいまの僕になれたのは、リーリエがいてくれたからと言うのが一番大きいと思うけど、遠坂がいてくれなければリーリエを生み出すこともなく、荒れ続けていたかもしれない、とも思う。
「何だよお前。僕のファンかよ。なんでそんなに僕のこと見てるんだよ」
気恥ずかしくなって、僕は誤魔化すようにそんなことを口にしてしまっていた。
「そうだよ、ファンだよ。ワタシはあんたのファンなのっ。いつも元気で優しい百合乃ちゃんのことが好きだったよ。でもね、克樹。ワタシはその百合乃ちゃんのお兄ちゃんをしっかりやってる克樹のこと、見てたよ。だからワタシは、あんたのファンなんだよ!」
「な、何を言ってんだよっ」
言ってしまった僕の方が恥ずかしくなるようなことを言い返されて、僕は顔が熱くなるのも感じていた。
でも遠坂は、そんな僕の顔を見ながら、泣きそうな顔をしている。
「夏姫のこと、話した方がいいんじゃないかと思ってる。口止めされてるけど、克樹には話しておいた方がいいと思う。でもね、克樹。夏姫のこと助けようとしたら。克樹はあの子のいろんなことを背負わないといけないと思う」
「……そんな、状況なのか?」
「うん。そういう問題なの。克樹はたぶん、聞いちゃったら放っておけない。そういう奴だもん、克樹って」
泣きそうな顔で、遠坂は笑う。
かなり重い問題だろうことは予想してた。夏姫がまったく連絡をよこさないくらいだ、けっこう酷い状況なんだろうとは思ってた。
それに遠坂の言うこともわかる。
僕は何か問題がある人を見かけたら、放っておけない。無理や無茶はできないし、自分のできる範囲でしかやらないけど、性分なのか、完全には放っておくことなんてできない。
遠坂の指摘は正しい。それは僕自身がよく知ってる。
「中途半端に助けようとなんてしたら、たぶん夏姫が迷惑する。克樹も大変なことになる。だから教えて。克樹にとって、夏姫って、どんな人なの?」
「僕にとって夏姫は……」
微笑みながら問うてくる遠坂に、僕は自分に答えを問うていた。
これまで見てきた夏姫の顔が浮かぶ。彼女の言葉を思い出す。
そして一番最初の、夏姫の存在を初めて知ったときの想いが、いまは僕の中で育って大きくなっていることを意識する。
「僕にとって夏姫は――」
泣きそうな顔で笑ってる遠坂に、僕は僕の想いを告げた。
*
「てめぇふざけんなっ。ありゃあいったいなんだ?!」
かかってきた通話着信の名前を見て、猛臣は応答ボタンを押すと同時に叫ぶように言葉を放った。
『あんまりな挨拶ね。いきなり何なのかしら?』
「何なのも何もねぇ。いったい何なんだっ、あの中里灯理って奴は!」
『あぁ、なるほど。彼女と接触したのね』
猛臣の怒気にも怯むことなく、電話の相手は涼やかな声で応答する。
連泊しているホテルの部屋のテーブルに転がっているスレート端末には、ほんの少し前に届いた中里灯理の情報が表示されていた。
ソファに座り、テーブルに脚を投げ出して携帯端末に耳を当てている猛臣の顔は、怒りに赤く染まっている。
「聞いてねぇぞ、モルガーナ! スフィアカップに参加してない奴がなんでエリキシルスフィアを持ってやがるっ。いったいどういうことなんだ!!」
SR社の研究所に出入りしているという仕事の関係上、何度か直接話し、メールなどで連絡を取ることもあるモルガーナ。
エリキシルバトルの主催者が彼女であることは、少ない情報を頼りに調べていっても、猛臣が気づくまでにはさほど時間は必要なかった。
五年ほどの間にロボット業界を席巻したと言っても過言ではないスフィアドール。その原動力となり、製造方法は不明で、同程度のものを再現することもできないスフィア。
その一番重要な部分であるスフィアコアは、多くの謎に包まれている。
エリキシルバトルに参加する前でも、SR社の動きやロボット業界の動向を探っていれば、誰かひとりの人間の意図に左右されていることは感じ取ることができる。それを槙島という家の力を使って調べていけば、モルガーナにたどり着くことができた。
しかし彼女の存在に気づくときには、彼女の持つ影響力の強さ、そしてその範囲の広さに気づくことになる。
いまこの世界にモルガーナは不可欠なほどに重要であり、ヘタに触れば超大国であっても揺るがしかねない。それほどの力をはっきりと見出すことができるわけではなかったが、そう思えるほどの雰囲気を、猛臣は感じていた。
そして巧妙に存在を隠されつつも、たどり着く者にはそうしたことに気がつくよう仕組まれているようだった。
猛臣の知る限り、エリキシルバトルなどというものを開催可能な力と、現実離れした現象を起こしうる存在は、モルガーナしかいなかった。
そのことを指摘した猛臣に、モルガーナはあっさり自分が主催者であることを認めた。それからは、仕事以外のことでも連絡を取る機会が生まれていた。
『どうなっていると言われても、彼女もまたエリキシルバトルの参加者というだけの話よ。エイナから聞いているでしょう? 参加資格があるのは特別なスフィアを持つ者。決してスフィアカップの地方大会の優勝者と準優勝者に限定はしていないわ』
「ふざけんじゃねぇ! だったら他に中里灯理みたいな奴が何人いるのか教えやがれ!」
『それは無理な話ね。貴方にだけ情報を与えるなんて優遇はできないのよ、猛臣君。スフィアの買い取って集めることを認めただけでも、貴方のことは充分優遇していると思うのだけど?』
「……てめぇ」
映像のない通話オンリーの携帯端末の表示を睨みつけ、目の前にいたら殴りたい気持ちを舌打ちして堪える。
エリキシルバトルに参加し、自分と同じ特別なスフィアを持つ相手の中から参加者を捜し始めた猛臣は、エリキシルスフィアを買い取るという方法によって集めることにした。
猛臣にとってピクシードール、エリキシルドールで戦うこともバトルならば、資金という力を使って行うものも、戦いのひとつであったから。その方法を採ることにためらいはなかった。
それにストップをかけるべく連絡をしてきたのは、モルガーナ。
一度は禁止された買い取りはしかし、中盤戦に入ってから解禁されていた。
必ず連絡が取れるわけではなかったが、買い取りが許可されたことも、主催者と直接連絡が取れることも確かに優遇ではあったが、イレギュラーな参加者がいることに納得ができるわけではなかった。
『それで、連絡した用件だけれど、貴方が会社に手配の依頼してきた部品の都合がついたわ。さっきの件のお詫びというわけではないけれど、最優先で出荷するよう指示しておいたから』
「あぁ、もう届いてるよ」
ちらりと簡易デスクに目を走らせた猛臣。
そこには朝に届いた宅配便のダンボールが置かれている。まだ依頼したすべてのパーツが揃ったわけではないが、最低限のものは届いていた。
『それともうひとつ、貴方が興味を持ちそうな情報が入ってきたから、まとめさせておいたわ。そろそろ届いてるんじゃないかしら?』
「情報?」
言ってる間にスレート端末がメールの着信を告げた。
携帯端末を左手で耳に当てたまま、伸ばした右手でテーブルの上のスレート端末を操作し、メールを表示する。
「……なるほど。これはまた」
『満足していただけたかしら?』
「あぁ、充分だ。ありがとよ」
『これからも良い戦いを期待しているわ』
それだけ言って、モルガーナからの通話が切断された。
携帯端末をテーブルに置いた猛臣は、スレート端末を手に取り、情報を眺めていく。
その口元には、不適な笑みが浮かんでいた。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました
フルーツパフェ
大衆娯楽
とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。
曰く、全校生徒はパンツを履くこと。
生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?
史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。



幼なじみとセックスごっこを始めて、10年がたった。
スタジオ.T
青春
幼なじみの鞠川春姫(まりかわはるひめ)は、学校内でも屈指の美少女だ。
そんな春姫と俺は、毎週水曜日にセックスごっこをする約束をしている。
ゆるいイチャラブ、そしてエッチなラブストーリー。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

GAME CHANGER 日本帝国1945からの逆襲
俊也
歴史・時代
時は1945年3月、敗色濃厚の日本軍。
今まさに沖縄に侵攻せんとする圧倒的戦力のアメリカ陸海軍を前に、日本の指導者達は若者達による航空機の自爆攻撃…特攻 で事態を打開しようとしていた。
「バカかお前ら、本当に戦争に勝つ気があるのか!?」
その男はただの学徒兵にも関わらず、平然とそう言い放ち特攻出撃を拒否した。
当初は困惑し怒り狂う日本海軍上層部であったが…!?
姉妹作「新訳 零戦戦記」共々宜しくお願い致します。
共に
第8回歴史時代小説参加しました!

【R18】俺は変身ヒーローが好きだが、なったのは同級生の女子でした。一方の俺は悪の組織に捕らえられマッドサイエンティストにされた
瀬緋 令祖灼
SF
変身ヒーロー好きの男子高校生山田大輝は、普通の学生生活を送っていたが、気が晴れない。
この町には侵略を企む悪の組織がいて、変身ヒーローがいる。
しかし、ヒーローは自分ではなく、同級生の知っている女子、小川優子だった。
しかも、悪の組織に大輝は捕まり、人質となりレッドである優子は陵辱を受けてしまう。大輝は振り切って助けようとするが、怪人に致命傷を負わされた。
救急搬送で病院に送られ命は助かったが、病院は悪の組織のアジトの偽装。
地下にある秘密研究所で大輝は改造されてマッドサイエンティストにされてしまう。
そんな時、変身ヒーローをしている彼女、小川優子がやって来てしまった。
変身ヒーローの少女とマッドサイエンティストの少年のR18小説
実験的に画像生成AIのイラストを使っています。
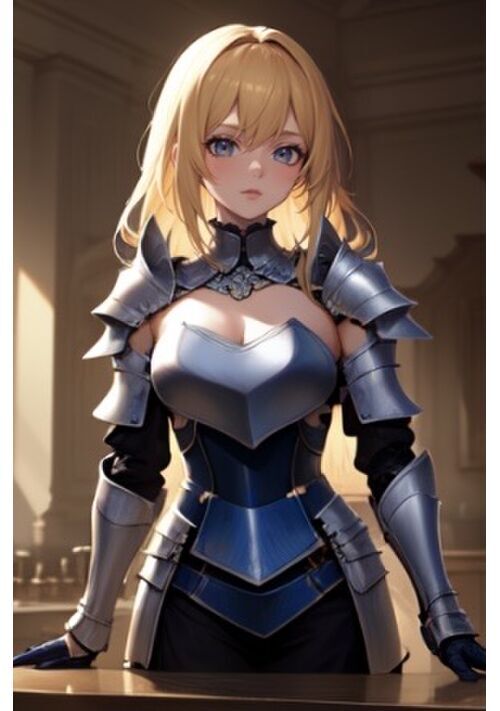
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















