51 / 150
第三部 第一章 チェイントラブル
第三部 極炎(クリムゾン)の怒り 第一章 2
しおりを挟む
* 2 *
――空が綺麗だな。
梅雨明け宣言もされてないのに、すっかり夏の雰囲気のある空を、僕は机に頬杖をつきながら眺めていた。
「克樹。途中まで一緒に帰ろ?」
担任教師の呪文に近い連絡事項を聞き流し、立ち上がって礼をし終わったと思った途端にやってきたのは、夏姫。
――なんでこう、こいつはいつもこうなんだか。
いまから二ヶ月前、灯理と戦っていたときには押し倒したりとかいろいろやっていたというのに、男に対して警戒心がない。最初からそんな感じではあったけど、何を考えてるのかわかりゃしない。
ただまぁ、あのとき以降は、別に何かしたりはしてなかったが。
と言うか、責任取ってもらうから、って言葉は、思った以上に重い。
黙ってる僕のことを小首を傾げながら眺めてる夏姫。
夏服に切り替わったからとは言え、梅雨時期で肌寒いと感じる日もあるこの頃だから、上着を羽織ってないだけの白いブラウスと黒っぽいジャンパースカート姿の彼女。
可愛いってことで女子にも、そして何より男子にも人気の高いジャンパスカートは、ほどよく大きい夏姫の胸を強調している。
長袖ではあるけど薄手のブラウスは、微かにその下の水色のキャミソールがうっすらと透けて見えていた。
「何? どうかしたの?」
「いや、ブラは透けないんだな、って」
「またそんなこと言って……。そんなだから女子から嫌われるんだよ? 別にアタシはもう、あんまり気にしてないけど」
「ったく」
さすがにたいしてつき合いのない他のクラスの女子ならともかく、もうつき合いが短いとは言えない夏姫になると、これまでちょこちょこ言ってきたような言葉じゃ効きゃしないみたいだ。
かと言って押し倒して「いいよ」なんて言われた日には僕の方がどうしていいのかわからなくなる。
――何か考えとかないとなぁ。
あんまり警戒されないのも問題だと思う僕は、何かいい方法はないかと考えつつ、授業用のタブレット端末なんかを鞄に仕舞い込み、帰る準備をする。
「本当、ここんところ仲がいいよね、夏姫と克樹。何かあったの?」
そんなことを言いながらやってきたのは、遠坂明美。
女子としては少し背が高めの夏姫よりももう少し背が高い彼女は、相変わらず強調するもののない胸を、座ってる僕の視線の位置に見せつけながら、不審そうな目を向けてくる。
「何かあったってことは、……えぇっと、ピクシードールのことで世話になってるからさ。ね? 克樹」
「こっちに振るなよ。別に夏姫とつき合ってるわけじゃないし、ドール関係で夏姫がすり寄ってきてるだけだ」
「すり寄ってるって……。克樹、あんたねぇ!」
「ふぅん」
前屈みになって睨みつけてくる夏姫の横で、さらに不信感を深めた顔で僕と夏姫のことを交互に見ている遠坂。
遠坂を押し倒したのは……、まだ高校に入る前で、僕の気持ちがいまよりもぐちゃぐちゃのときだったから、未遂にはなったが、夏姫や灯理のときよりさらにヤバい感じになっていた。遠坂が警察に駆け込んだりしたら、僕には言い訳ができない程度に。
そんな関係だから警戒されるのは仕方ないが、そもそも遠坂が僕を避けないのが不思議なくらいだ。
「まぁ、何かあったら全部責任取ってもらうから、大丈夫だよ、明美。アタシはこいつにやられっぱなしになんてならないからさ」
「そういうことならいい、のかな? でも本当、気をつけないとダメだよ」
「わかってるって」
心配そうにしてる遠坂に対し、夏姫はにっこりとした笑みを僕に向けてくる。「わかってるよね」という言葉が籠もってそうな笑み。
そりゃあ僕はヒューマニティフェイスとかの報酬で、多いときは新卒サラリーマンの月収なんて目じゃないほどの収入があるときもあるけど、フェイスパーツの売れ行き次第だから安定はしていない。新型の制作にも取りかかってるけど、もう表情をつくる機能は充分にあるから、大きな変更も難しく、報酬は今後減りこそすれ増える可能性は高くない。
将来的にって意味であれば、女の子ひとりの責任くらい取れるようにはなれると思うけど、いまの段階で言われても正直怖いと思ってしまう。
――そんなに真面目に考える必要ないか。
夏姫とはそこまでのことにはなってないんだし、僕の気持ちが暴走してもリーリエがある程度のところでストップしてくれる。強引な手段だったりはするけど。
深く悩む必要がないことに気づいて、僕は口元にさらに深い笑みを浮かべて楽しそうにしてる夏姫から目を逸らした。
「でも明美。克樹ってけっこうイザってときにヘタレじゃない」
「あー、うん。そうなんだよね。もう一歩のところでヘタれるよね、克樹って」
「だからまぁ、大丈夫だよ」
ふたりにとって僕はいったいどんな奴になってるのか。納得したように頷き合う夏姫と遠坂に、僕は思わずため息を漏らしていた。
「でもヘタレでも克樹だって男なんだから、そのことは忘れちゃダメだよ」
「うん、わかってる。ありがとう」
「克樹も! あんまり女の子泣かせるようなことしちゃダメだよ」
「お前は僕の姉ちゃんか……」
「あははっ。……まぁ、部活行ってくるね」
僕たちの会話を聞きつつ、遠巻きにしていた人物が近づいてきたのを見て、遠坂はそいつにちらりと視線を飛ばしてから教室を出ていった。
やってきたのは近藤。
もうすっかり伸びてきた髪を角刈りみたいに立てている近藤は、一応遠坂とは和解している。
と言っても通り魔として彼女を襲い、車に轢かれそうになった原因をつくったのだ、完全に修復したとは言い難い距離感だった。
「ま、帰ろう。克樹、近藤」
「あぁ」
「そうだな」
微妙な空気を吹き飛ばすように言った夏姫の声に、僕は席を立ってふたりと一緒に教室を出た。
*
「ここんとこ、平和だね」
先に靴を履き替えて昇降口に出ていた夏姫が、振り返って僕と近藤にそう声をかけてきた。
「中里の後は、敵に出会ってないからな」
「まぁ、平和だね」
靴を履き終えて昇降口を出た僕は、七月初旬の晴れ渡った空を仰ぐ。
もうすっかり暑くなってるって言うのに、校庭では運動部の連中が練習を始めていた。
校庭の大部分を使うのはサッカー部で、隅の方では部員が女子中心の弱小陸上部が準備運動をしてる。部員にいろいろ指示を出してるらしい、男子と間違えそうになる体型の奴が、たぶん遠坂だろう。
灯理と戦って以降は、本当に平和だ。
レーダーに新しいエリキシルスフィアの反応が引っかかることもない。
夏姫、近藤と連続して出会った後は、灯理と出会うまでは五ヶ月くらい間があったんだから、エリキシルソーサラーとの遭遇率はそんなものなのかも知れない、とも思う。
でもバトルはもう中盤戦に入ってるんだ、僕たちの知らないところで戦ってる奴がいることもまた、確かだった。
こちらから打って出ることも考えなくもなかったが、バトル参加者がどこにいるのかもわからないんじゃ、参加者の可能性がある特別なスフィアを持つ人をしらみつぶしにするしかない。その所在を探すだけでも手間か金がかかるのは確かだから、そこまではやる気がなかった。
「でも、バトルが終わったわけじゃない」
並んで校門に向かって歩く途中、ぽつりと言ったのは近藤。
隣に立つ近藤は、僕と夏姫のことを見ながら言う。
「いつ敵と出会わないとも限らない。警戒は必要だろう」
「もっちろん、警戒はしてるよ」
学校指定の鞄を軽く叩いて返事したのは夏姫。
エリキシルバトルアプリは携帯端末にインストールして使うもので、レーダーはアプリの機能だけど、どういう理屈なのか、エリキシルスフィアがある程度近くにないと機能しない。スフィアを受信機として使用しているらしい。
夏姫が叩いた鞄の中にはもちろん、僕と近藤の鞄の中にもエリキシルスフィアを搭載したピクシードールが入ってる。
敵が現れれば携帯が警告を発するように設定もしてあるし、充分ではないかも知れないけど、警戒は怠っていなかった。
「明日はまた克樹の家でいいんでしょ?」
「あ、うん。まぁ、仕方ないね」
僕の顔を覗き込むようにして問うてくる夏姫に、ため息を吐きそうになりながらも応える。
灯理の件があって以降、夏姫や近藤、灯理の三人は時間がある週末なんかには僕の家に集まるようになっていた。
主にやってるのはピクシーバトル。
エリキシルバトルじゃなく、アライズしないでのバトルだ。僕の家のLDKはそこそこ広いって言っても、エリキシルドールが飛び回るほどはない。
一応敵同士ではある僕たちだけど、いまのところは協力するってことで、戦闘訓練をしてお互いの力を高め合っている。
なんで僕の家なんだ、と思うけど、独り暮らしで部屋が狭く集合住宅の夏姫と近藤の家というわけにはいかなかったし、親が帰ってきたりお手伝いの人がいたりする灯理の家というわけにもいかない。親がまず帰ってこないし、広さもそこそこの上、灯理を除くと家が近い僕のとこが最適だったからだろう。自然とそうなっていた。
――なんか最近、そればっかりじゃないけど。
家が少し離れてるから灯理が来るのは週末が中心だけど、夏姫は平日でもたまに来ることがあって、夕食をつくってくれたりするし、そのときに近藤も彼女に呼ばれてやってくることもあった。
――なんか僕の家がサロンみないになってるよな。
僕がいなくてもリーリエに管理されてるから家に入ることはできるし、何かあればリーリエが記録もしてるし連絡もしてくれる。
勝手に、というのとは違うけど、なんかここのところは出入り自由の集合所みたいな雰囲気になりつつあった。
『ねぇ、おにぃちゃん。気づいてる?』
「うん、さすがにね」
イヤホンマイクの外部スピーカーから声を発したリーリエの指摘に、僕は頷いていた。
携帯端末とかで見てるわけじゃないから正確な距離まではわからないけど、校門のところに白いスカートの裾が見え隠れしてる。
下校する他の奴らに注目されてるっぽい彼女の存在に気づいたらしい夏姫が、隣で眉を顰めていくのが見えた。
レーダーを見てなかったからここに来るまで気づかなかったけど、もうそこにいるのが誰なのか、たどり着かなくてもわかる。
「あ、克樹さん。こんにちは」
たぶん、僕たちとの距離をずっと確認していたんだろう。
校門を出た直後、膝上丈のスカートともに長く細い髪をふわりとはためかせて向き直ったのは、クリームホワイトの制服を身につけ、白地に赤いラインが引かれた医療用スマートギアを被ってる女の子。
中里灯理。
「こんにちは、夏姫さん、近藤さんも」
「こんにちは、灯理」
「あぁ、こんにちは」
にっこり笑う灯理に対し、夏姫と近藤の表情は渋い。
灯理の行動はけっこう突発的だ。
突然こうやって学校に現れたり、休日に遊びに誘ってきたりする。そうしたときの相手の反応を楽しんでる様子すらある。
本当にダメなときに押し進めてきたり、嫌がらせでやってくるというわけではないみたいだけど、天然なのか、意識的にやってるのかいまひとつわからない。
その上、いまは視力を失って話題に出ることはほとんどなくなったとは言え、灯理は若い画家として有名だったんだ。そんな彼女が僕や夏姫たちを訊ねて二度三度と学校にやってきたりしたら、校内でも噂になったりもする。
できるだけ笑顔を返そうと思っても、僕の顔も引きつらざるを得なかった。
「今日はどうしたの? 灯理」
「えぇ。今日は少し克樹さんに用事がありまして。後ほど家にお伺いしようかと思ったのですが、この時間でしたらまだ学校にいらっしゃるかと思って、待ちきれずにここまで来てしまいました」
「そ、そう」
ニコニコとした笑みを浮かべながら、声を控えることなく話す灯理に、夏姫は怯むように勢いを失う。まだまだ多い下校する生徒の不躾な視線が痛い。
「用事って、なんだったっけ?」
夏姫も近藤も驚いてるが、それは僕だって同じだ。今日来るって話は事前には聞いてなかったと思う。
「先週話してあったではないですか。今日PCWにフレイとフレイヤのパーツが一部届くかも知れないと。一緒に取りに行きましょうと言ったらあのとき、克樹さんは頷いてくださったでしょう? それで、先ほどお店からパーツが届いたと連絡があったのですよ」
「……そう思えば、そんな話もあったね」
僕とリーリエとで戦った灯理のフレイとフレイヤは、首を切り落としたときにメインフレームを切断していた。
フルスペックではないけど第五世代のメインフレームはとりあえず修復するってことでPCWを紹介して、強化のためのパーツを相談して注文もした。
確か先週、一緒に取りに行こうといわれたときに頷いたのは憶えてるけど、まさか届いた当日に事前連絡なしに行くことになるとは思ってなかった。
――まぁこの後、特別用事があるわけじゃないからいいんだけど。
「さぁ克樹さん。行きましょう」
「お、おい」
そう言って僕の腕に自分の腕を、どころか身体ごと絡みつけてくる灯理。
小柄な割に夏姫以上の大きな胸が、制服越しなのに柔らかく僕の腕に押しつけられる。
――くっ……。やっぱり柔らかいな。
別に大きい方が好きってわけじゃないし、夏姫の胸だってけっこう大きいと思うが、それよりも大きい灯理の胸は柔らかさが違う。さらに夏服になってからは、制服の下のブラの感触までわかってしまう。
しかしこの腕に抱きつくような体勢は、医療用スマートギアを被ってるっていう少し奇異に見られるところはあっても、それを超えるくらいに可愛らしい灯理だったりするわけだから、夏姫や近藤の視線ばかりじゃなく、他の人たちからの視線も痛くて仕方がない。
『もうっ! 何やってるの? 灯理っ。おにぃちゃんから離れて!!』
「そうだよ、灯理。克樹が迷惑してるでしょっ」
「そんな、これくらいは親しい仲では普通のスキンシップでしょう?」
「近藤にはそこまでのことしないでしょ!」
「そうでしたでしょうか?」
「場所を考えなさい!」
「それは場所を考えれば、してもいいということですか?」
『何でもいいから、おにぃちゃんから離れて!』
「仕方ないですね。……もう少し遊んでいたかったのですが」
灯理を睨みつけている夏姫に対して、睨まれた彼女は気にした風もなく涼しい笑みを返していたが、どうにか抱きつくのだけはやめてくれた。……僕にだけ聞こえる程度の声で呟いた最後の言葉は、聞こえなかったことにした。
何かとスキンシップをしてくる灯理だけど、夏姫がいるときはとくに挑発的にやってきてるような気がする。
エリキシルソーサラーが現れなくて平和ではあるんだけど、いまひとつ僕の周りは騒がしくて仕方がなかった。
――もう少し平穏な方が、僕は好きなんだけどね……。
エリキシルバトルが続いてる間は、ソーサラーごとエリキシルスフィアを集めると決めたんだから、多少騒がしくなるのは覚悟の上だったけど、こういう騒がしさは勘弁してほしい。
「夏姫さんも一緒に行きませんか?」
「知ってるんでしょ、灯理。アタシは今日バイトあるんだって」
「そうでしたね。すみません。失念していました」
忘れてたなんて絶対嘘だと思うが、素直に謝る灯理に夏姫は重苦しいため息を吐き出すだけだった。
「と、とにかく行ってくる」
「行ってらっしゃい、克樹っ」
「またな、克樹」
『うん、行ってくる。またね、夏姫、誠。ちゃーんとあたしが見てるから、安心して!』
「ん、わかった。リーリエ、頼むね」
そんなやりとりをして、僕は灯理とともに駅に向かって歩き始める。
イヤホンマイクじゃリーリエには見えないからだろうか、それとも夏姫に見せつけるためなのか、こっそりと手を繋いできた灯理の手は、意外と強くつかまれていて振り払うことはできそうになかった。
――何を考えてるんだか。灯理も、夏姫も。
灯理に聞こえないように小さくため息を吐きながら、僕は背中に突き刺さる視線に気づかない振りをしていた。
人混みの中を遠ざかっていく克樹と灯理の背中を睨みつけていた夏姫は、深くため息を漏らしていた。
「いいのか? このままふたりで行かせて」
夏姫とともに取り残されるように立っていた近藤が声をかけてくる。
「仕方ないでしょ。アタシはこの後バイトなんだから。気になるんだったら近藤が一緒に行けばいいんじゃないの?」
「俺も今日はバイトだし、そういうことじゃないんだが……」
言葉を濁す近藤を、夏姫は睨みつける。
「何?」
「いや、いい……」
身体が大きい割に、通り魔事件以降あまり強く出てくることがなくなった近藤は、夏姫の視線に首を縮めていた。
近藤が言いたいことも、夏姫はだいたいわかっている。
克樹とは別につき合っているわけではないし、エリキシルバトルのことで一番最初に出会って協力するようになったというのはあっても、告白されたわけでも、こちらから告白したわけでもない。――する予定も、ない。
苛立っていても仕方ないのはわかっているし、克樹が灯理を選ぶならばそれも仕方がないと思うのだが、キスの予約までしたというのに、灯理にすり寄られているのを目の当たりにすると、苛立つのを抑えることもできない。
「まぁなんか、灯理の家の事情とかもあるみたいなんだけどね」
「家の事情?」
「うん」
克樹たちの姿がすっかり見えなくなったのを確認して、夏姫もまた駅の方向に向かって歩き始めた。近藤も並んで着いてくる。
「けっこう両親の仲がよくないらしいよ? さすがにあんまり細かいところまでは聞けないけど、そんなこと言ってた」
灯理とはふたりきりのときにいろんな話をしていることがあったが、家のことも話すことがあった。
画商であるという母親と、そこそこ名の知られた彫刻家である父親の間は、何かと揉めていることが多いという。揉める内容までは知らなかったが、忙しいのもあって両親が揃っていることは少なく、家に帰ってくること自体少ないということだった。
「なんか、両親がいなくて寂しいらしいんだよね」
「そうなのか。と言っても、それを言ったら克樹の家だってバトル始まってから一度も親が家に帰ってきたことないみたいだし、いまは独り暮らしをしてるオレや浜咲だって、そんなに変わらないだろう」
「……そう思えば、そっか」
不思議そうな顔をして身長差の分で見下ろしてくる近藤の言葉に、夏姫は自分や克樹たちの境遇を思い出す。
比べてみても、灯理だけが特別酷い境遇というわけではないように思えた。
――まぁでも、アタシがあんまり口を挟むことでもないしなぁ……。
克樹のジェスチャー程度の行動は、よほど相手が乗ってこない限り間違いが起こることはないと思うし、相手が誘ってきたとしても克樹の側にはいつもリーリエがいる。
克樹自身が行動を起こさない限りは大丈夫なのだろうと思うが、夏姫は胸の中にわだかまる不安を拭えなかった。
――灯理も、可愛いもんね。
女の子の夏姫から見ても、灯理は小柄で可愛らしく、羨ましくなるほどのスタイルをしている。性格の強引さはあれども、ジェスチャー以外ではヘタレで奥手な克樹に対しては、それくらいの方が近い道なのかもしれないとも思えた。
「あんまり聞いたことなかったが、浜咲は父親はいるんだろ?」
「あ、うん。いるよ。もうずいぶん会ってないけど」
事情を話していない近藤の質問に、夏姫はできるだけの笑みを浮かべて答える。
父親とはもう一年以上会っていなかった。
再就職に失敗し、酒に溺れた父親は、自分の妻が死んだときにも、酒を飲み歩いていた。
いまは仕事をしていて、アパートの家賃と、生活費の仕送りはしてくれていた。元々の仕事とは関係ない仕事は厳しいらしく、自分でつくった借金もあって、仕送りの金額は暮らしていくことができないほど。
足りない分はどうにかアルバイトで賄うことはできていたが、余裕はほとんどなかった。
「会いたくないのか?」
「んー。あんまり。会いたくはない、かなぁ」
「……済まん」
できるだけ笑っていたはずなのに、何かに気づいたのか、近藤が謝ってくる。
それに対して目を細めて笑って見せた夏姫は、まだ早い夏の陽射しが降り注いでくる青空を仰いで、会いたいと思えない父親のことを思い出していた。
もうふたりきりの肉親なのに、父親を恋しいとは思えなかった。
生活のすべてを春歌に任せ、ひとり飲んだくれ、時には暴力を振るっていた父親だったが、彼女の死を悲しんでいないということはない。自分の行動を悔いていないわけはない。
けれど夏姫は父親を許せなかった。春歌を死に追いやった彼を、どうしても許すことができなかった。
許したいという気持ちがないわけではなかったが、まだ胸の中に残るわだかまりが、自分の父親に対してどんな言葉で話していいのか、わからなくさせていた。
「ま、みんないろんな事情があるんだよ。アタシにも、灯理にも、克樹にも、もちろん近藤にもね。だからまぁ、とりあえずはいいかな、って」
「そうか」
悔いているように顔を歪ませている近藤に笑いかけつつも、夏姫は鞄を持っていない右手で、ずきずきと痛むような胸を押さえていた。
――空が綺麗だな。
梅雨明け宣言もされてないのに、すっかり夏の雰囲気のある空を、僕は机に頬杖をつきながら眺めていた。
「克樹。途中まで一緒に帰ろ?」
担任教師の呪文に近い連絡事項を聞き流し、立ち上がって礼をし終わったと思った途端にやってきたのは、夏姫。
――なんでこう、こいつはいつもこうなんだか。
いまから二ヶ月前、灯理と戦っていたときには押し倒したりとかいろいろやっていたというのに、男に対して警戒心がない。最初からそんな感じではあったけど、何を考えてるのかわかりゃしない。
ただまぁ、あのとき以降は、別に何かしたりはしてなかったが。
と言うか、責任取ってもらうから、って言葉は、思った以上に重い。
黙ってる僕のことを小首を傾げながら眺めてる夏姫。
夏服に切り替わったからとは言え、梅雨時期で肌寒いと感じる日もあるこの頃だから、上着を羽織ってないだけの白いブラウスと黒っぽいジャンパースカート姿の彼女。
可愛いってことで女子にも、そして何より男子にも人気の高いジャンパスカートは、ほどよく大きい夏姫の胸を強調している。
長袖ではあるけど薄手のブラウスは、微かにその下の水色のキャミソールがうっすらと透けて見えていた。
「何? どうかしたの?」
「いや、ブラは透けないんだな、って」
「またそんなこと言って……。そんなだから女子から嫌われるんだよ? 別にアタシはもう、あんまり気にしてないけど」
「ったく」
さすがにたいしてつき合いのない他のクラスの女子ならともかく、もうつき合いが短いとは言えない夏姫になると、これまでちょこちょこ言ってきたような言葉じゃ効きゃしないみたいだ。
かと言って押し倒して「いいよ」なんて言われた日には僕の方がどうしていいのかわからなくなる。
――何か考えとかないとなぁ。
あんまり警戒されないのも問題だと思う僕は、何かいい方法はないかと考えつつ、授業用のタブレット端末なんかを鞄に仕舞い込み、帰る準備をする。
「本当、ここんところ仲がいいよね、夏姫と克樹。何かあったの?」
そんなことを言いながらやってきたのは、遠坂明美。
女子としては少し背が高めの夏姫よりももう少し背が高い彼女は、相変わらず強調するもののない胸を、座ってる僕の視線の位置に見せつけながら、不審そうな目を向けてくる。
「何かあったってことは、……えぇっと、ピクシードールのことで世話になってるからさ。ね? 克樹」
「こっちに振るなよ。別に夏姫とつき合ってるわけじゃないし、ドール関係で夏姫がすり寄ってきてるだけだ」
「すり寄ってるって……。克樹、あんたねぇ!」
「ふぅん」
前屈みになって睨みつけてくる夏姫の横で、さらに不信感を深めた顔で僕と夏姫のことを交互に見ている遠坂。
遠坂を押し倒したのは……、まだ高校に入る前で、僕の気持ちがいまよりもぐちゃぐちゃのときだったから、未遂にはなったが、夏姫や灯理のときよりさらにヤバい感じになっていた。遠坂が警察に駆け込んだりしたら、僕には言い訳ができない程度に。
そんな関係だから警戒されるのは仕方ないが、そもそも遠坂が僕を避けないのが不思議なくらいだ。
「まぁ、何かあったら全部責任取ってもらうから、大丈夫だよ、明美。アタシはこいつにやられっぱなしになんてならないからさ」
「そういうことならいい、のかな? でも本当、気をつけないとダメだよ」
「わかってるって」
心配そうにしてる遠坂に対し、夏姫はにっこりとした笑みを僕に向けてくる。「わかってるよね」という言葉が籠もってそうな笑み。
そりゃあ僕はヒューマニティフェイスとかの報酬で、多いときは新卒サラリーマンの月収なんて目じゃないほどの収入があるときもあるけど、フェイスパーツの売れ行き次第だから安定はしていない。新型の制作にも取りかかってるけど、もう表情をつくる機能は充分にあるから、大きな変更も難しく、報酬は今後減りこそすれ増える可能性は高くない。
将来的にって意味であれば、女の子ひとりの責任くらい取れるようにはなれると思うけど、いまの段階で言われても正直怖いと思ってしまう。
――そんなに真面目に考える必要ないか。
夏姫とはそこまでのことにはなってないんだし、僕の気持ちが暴走してもリーリエがある程度のところでストップしてくれる。強引な手段だったりはするけど。
深く悩む必要がないことに気づいて、僕は口元にさらに深い笑みを浮かべて楽しそうにしてる夏姫から目を逸らした。
「でも明美。克樹ってけっこうイザってときにヘタレじゃない」
「あー、うん。そうなんだよね。もう一歩のところでヘタれるよね、克樹って」
「だからまぁ、大丈夫だよ」
ふたりにとって僕はいったいどんな奴になってるのか。納得したように頷き合う夏姫と遠坂に、僕は思わずため息を漏らしていた。
「でもヘタレでも克樹だって男なんだから、そのことは忘れちゃダメだよ」
「うん、わかってる。ありがとう」
「克樹も! あんまり女の子泣かせるようなことしちゃダメだよ」
「お前は僕の姉ちゃんか……」
「あははっ。……まぁ、部活行ってくるね」
僕たちの会話を聞きつつ、遠巻きにしていた人物が近づいてきたのを見て、遠坂はそいつにちらりと視線を飛ばしてから教室を出ていった。
やってきたのは近藤。
もうすっかり伸びてきた髪を角刈りみたいに立てている近藤は、一応遠坂とは和解している。
と言っても通り魔として彼女を襲い、車に轢かれそうになった原因をつくったのだ、完全に修復したとは言い難い距離感だった。
「ま、帰ろう。克樹、近藤」
「あぁ」
「そうだな」
微妙な空気を吹き飛ばすように言った夏姫の声に、僕は席を立ってふたりと一緒に教室を出た。
*
「ここんとこ、平和だね」
先に靴を履き替えて昇降口に出ていた夏姫が、振り返って僕と近藤にそう声をかけてきた。
「中里の後は、敵に出会ってないからな」
「まぁ、平和だね」
靴を履き終えて昇降口を出た僕は、七月初旬の晴れ渡った空を仰ぐ。
もうすっかり暑くなってるって言うのに、校庭では運動部の連中が練習を始めていた。
校庭の大部分を使うのはサッカー部で、隅の方では部員が女子中心の弱小陸上部が準備運動をしてる。部員にいろいろ指示を出してるらしい、男子と間違えそうになる体型の奴が、たぶん遠坂だろう。
灯理と戦って以降は、本当に平和だ。
レーダーに新しいエリキシルスフィアの反応が引っかかることもない。
夏姫、近藤と連続して出会った後は、灯理と出会うまでは五ヶ月くらい間があったんだから、エリキシルソーサラーとの遭遇率はそんなものなのかも知れない、とも思う。
でもバトルはもう中盤戦に入ってるんだ、僕たちの知らないところで戦ってる奴がいることもまた、確かだった。
こちらから打って出ることも考えなくもなかったが、バトル参加者がどこにいるのかもわからないんじゃ、参加者の可能性がある特別なスフィアを持つ人をしらみつぶしにするしかない。その所在を探すだけでも手間か金がかかるのは確かだから、そこまではやる気がなかった。
「でも、バトルが終わったわけじゃない」
並んで校門に向かって歩く途中、ぽつりと言ったのは近藤。
隣に立つ近藤は、僕と夏姫のことを見ながら言う。
「いつ敵と出会わないとも限らない。警戒は必要だろう」
「もっちろん、警戒はしてるよ」
学校指定の鞄を軽く叩いて返事したのは夏姫。
エリキシルバトルアプリは携帯端末にインストールして使うもので、レーダーはアプリの機能だけど、どういう理屈なのか、エリキシルスフィアがある程度近くにないと機能しない。スフィアを受信機として使用しているらしい。
夏姫が叩いた鞄の中にはもちろん、僕と近藤の鞄の中にもエリキシルスフィアを搭載したピクシードールが入ってる。
敵が現れれば携帯が警告を発するように設定もしてあるし、充分ではないかも知れないけど、警戒は怠っていなかった。
「明日はまた克樹の家でいいんでしょ?」
「あ、うん。まぁ、仕方ないね」
僕の顔を覗き込むようにして問うてくる夏姫に、ため息を吐きそうになりながらも応える。
灯理の件があって以降、夏姫や近藤、灯理の三人は時間がある週末なんかには僕の家に集まるようになっていた。
主にやってるのはピクシーバトル。
エリキシルバトルじゃなく、アライズしないでのバトルだ。僕の家のLDKはそこそこ広いって言っても、エリキシルドールが飛び回るほどはない。
一応敵同士ではある僕たちだけど、いまのところは協力するってことで、戦闘訓練をしてお互いの力を高め合っている。
なんで僕の家なんだ、と思うけど、独り暮らしで部屋が狭く集合住宅の夏姫と近藤の家というわけにはいかなかったし、親が帰ってきたりお手伝いの人がいたりする灯理の家というわけにもいかない。親がまず帰ってこないし、広さもそこそこの上、灯理を除くと家が近い僕のとこが最適だったからだろう。自然とそうなっていた。
――なんか最近、そればっかりじゃないけど。
家が少し離れてるから灯理が来るのは週末が中心だけど、夏姫は平日でもたまに来ることがあって、夕食をつくってくれたりするし、そのときに近藤も彼女に呼ばれてやってくることもあった。
――なんか僕の家がサロンみないになってるよな。
僕がいなくてもリーリエに管理されてるから家に入ることはできるし、何かあればリーリエが記録もしてるし連絡もしてくれる。
勝手に、というのとは違うけど、なんかここのところは出入り自由の集合所みたいな雰囲気になりつつあった。
『ねぇ、おにぃちゃん。気づいてる?』
「うん、さすがにね」
イヤホンマイクの外部スピーカーから声を発したリーリエの指摘に、僕は頷いていた。
携帯端末とかで見てるわけじゃないから正確な距離まではわからないけど、校門のところに白いスカートの裾が見え隠れしてる。
下校する他の奴らに注目されてるっぽい彼女の存在に気づいたらしい夏姫が、隣で眉を顰めていくのが見えた。
レーダーを見てなかったからここに来るまで気づかなかったけど、もうそこにいるのが誰なのか、たどり着かなくてもわかる。
「あ、克樹さん。こんにちは」
たぶん、僕たちとの距離をずっと確認していたんだろう。
校門を出た直後、膝上丈のスカートともに長く細い髪をふわりとはためかせて向き直ったのは、クリームホワイトの制服を身につけ、白地に赤いラインが引かれた医療用スマートギアを被ってる女の子。
中里灯理。
「こんにちは、夏姫さん、近藤さんも」
「こんにちは、灯理」
「あぁ、こんにちは」
にっこり笑う灯理に対し、夏姫と近藤の表情は渋い。
灯理の行動はけっこう突発的だ。
突然こうやって学校に現れたり、休日に遊びに誘ってきたりする。そうしたときの相手の反応を楽しんでる様子すらある。
本当にダメなときに押し進めてきたり、嫌がらせでやってくるというわけではないみたいだけど、天然なのか、意識的にやってるのかいまひとつわからない。
その上、いまは視力を失って話題に出ることはほとんどなくなったとは言え、灯理は若い画家として有名だったんだ。そんな彼女が僕や夏姫たちを訊ねて二度三度と学校にやってきたりしたら、校内でも噂になったりもする。
できるだけ笑顔を返そうと思っても、僕の顔も引きつらざるを得なかった。
「今日はどうしたの? 灯理」
「えぇ。今日は少し克樹さんに用事がありまして。後ほど家にお伺いしようかと思ったのですが、この時間でしたらまだ学校にいらっしゃるかと思って、待ちきれずにここまで来てしまいました」
「そ、そう」
ニコニコとした笑みを浮かべながら、声を控えることなく話す灯理に、夏姫は怯むように勢いを失う。まだまだ多い下校する生徒の不躾な視線が痛い。
「用事って、なんだったっけ?」
夏姫も近藤も驚いてるが、それは僕だって同じだ。今日来るって話は事前には聞いてなかったと思う。
「先週話してあったではないですか。今日PCWにフレイとフレイヤのパーツが一部届くかも知れないと。一緒に取りに行きましょうと言ったらあのとき、克樹さんは頷いてくださったでしょう? それで、先ほどお店からパーツが届いたと連絡があったのですよ」
「……そう思えば、そんな話もあったね」
僕とリーリエとで戦った灯理のフレイとフレイヤは、首を切り落としたときにメインフレームを切断していた。
フルスペックではないけど第五世代のメインフレームはとりあえず修復するってことでPCWを紹介して、強化のためのパーツを相談して注文もした。
確か先週、一緒に取りに行こうといわれたときに頷いたのは憶えてるけど、まさか届いた当日に事前連絡なしに行くことになるとは思ってなかった。
――まぁこの後、特別用事があるわけじゃないからいいんだけど。
「さぁ克樹さん。行きましょう」
「お、おい」
そう言って僕の腕に自分の腕を、どころか身体ごと絡みつけてくる灯理。
小柄な割に夏姫以上の大きな胸が、制服越しなのに柔らかく僕の腕に押しつけられる。
――くっ……。やっぱり柔らかいな。
別に大きい方が好きってわけじゃないし、夏姫の胸だってけっこう大きいと思うが、それよりも大きい灯理の胸は柔らかさが違う。さらに夏服になってからは、制服の下のブラの感触までわかってしまう。
しかしこの腕に抱きつくような体勢は、医療用スマートギアを被ってるっていう少し奇異に見られるところはあっても、それを超えるくらいに可愛らしい灯理だったりするわけだから、夏姫や近藤の視線ばかりじゃなく、他の人たちからの視線も痛くて仕方がない。
『もうっ! 何やってるの? 灯理っ。おにぃちゃんから離れて!!』
「そうだよ、灯理。克樹が迷惑してるでしょっ」
「そんな、これくらいは親しい仲では普通のスキンシップでしょう?」
「近藤にはそこまでのことしないでしょ!」
「そうでしたでしょうか?」
「場所を考えなさい!」
「それは場所を考えれば、してもいいということですか?」
『何でもいいから、おにぃちゃんから離れて!』
「仕方ないですね。……もう少し遊んでいたかったのですが」
灯理を睨みつけている夏姫に対して、睨まれた彼女は気にした風もなく涼しい笑みを返していたが、どうにか抱きつくのだけはやめてくれた。……僕にだけ聞こえる程度の声で呟いた最後の言葉は、聞こえなかったことにした。
何かとスキンシップをしてくる灯理だけど、夏姫がいるときはとくに挑発的にやってきてるような気がする。
エリキシルソーサラーが現れなくて平和ではあるんだけど、いまひとつ僕の周りは騒がしくて仕方がなかった。
――もう少し平穏な方が、僕は好きなんだけどね……。
エリキシルバトルが続いてる間は、ソーサラーごとエリキシルスフィアを集めると決めたんだから、多少騒がしくなるのは覚悟の上だったけど、こういう騒がしさは勘弁してほしい。
「夏姫さんも一緒に行きませんか?」
「知ってるんでしょ、灯理。アタシは今日バイトあるんだって」
「そうでしたね。すみません。失念していました」
忘れてたなんて絶対嘘だと思うが、素直に謝る灯理に夏姫は重苦しいため息を吐き出すだけだった。
「と、とにかく行ってくる」
「行ってらっしゃい、克樹っ」
「またな、克樹」
『うん、行ってくる。またね、夏姫、誠。ちゃーんとあたしが見てるから、安心して!』
「ん、わかった。リーリエ、頼むね」
そんなやりとりをして、僕は灯理とともに駅に向かって歩き始める。
イヤホンマイクじゃリーリエには見えないからだろうか、それとも夏姫に見せつけるためなのか、こっそりと手を繋いできた灯理の手は、意外と強くつかまれていて振り払うことはできそうになかった。
――何を考えてるんだか。灯理も、夏姫も。
灯理に聞こえないように小さくため息を吐きながら、僕は背中に突き刺さる視線に気づかない振りをしていた。
人混みの中を遠ざかっていく克樹と灯理の背中を睨みつけていた夏姫は、深くため息を漏らしていた。
「いいのか? このままふたりで行かせて」
夏姫とともに取り残されるように立っていた近藤が声をかけてくる。
「仕方ないでしょ。アタシはこの後バイトなんだから。気になるんだったら近藤が一緒に行けばいいんじゃないの?」
「俺も今日はバイトだし、そういうことじゃないんだが……」
言葉を濁す近藤を、夏姫は睨みつける。
「何?」
「いや、いい……」
身体が大きい割に、通り魔事件以降あまり強く出てくることがなくなった近藤は、夏姫の視線に首を縮めていた。
近藤が言いたいことも、夏姫はだいたいわかっている。
克樹とは別につき合っているわけではないし、エリキシルバトルのことで一番最初に出会って協力するようになったというのはあっても、告白されたわけでも、こちらから告白したわけでもない。――する予定も、ない。
苛立っていても仕方ないのはわかっているし、克樹が灯理を選ぶならばそれも仕方がないと思うのだが、キスの予約までしたというのに、灯理にすり寄られているのを目の当たりにすると、苛立つのを抑えることもできない。
「まぁなんか、灯理の家の事情とかもあるみたいなんだけどね」
「家の事情?」
「うん」
克樹たちの姿がすっかり見えなくなったのを確認して、夏姫もまた駅の方向に向かって歩き始めた。近藤も並んで着いてくる。
「けっこう両親の仲がよくないらしいよ? さすがにあんまり細かいところまでは聞けないけど、そんなこと言ってた」
灯理とはふたりきりのときにいろんな話をしていることがあったが、家のことも話すことがあった。
画商であるという母親と、そこそこ名の知られた彫刻家である父親の間は、何かと揉めていることが多いという。揉める内容までは知らなかったが、忙しいのもあって両親が揃っていることは少なく、家に帰ってくること自体少ないということだった。
「なんか、両親がいなくて寂しいらしいんだよね」
「そうなのか。と言っても、それを言ったら克樹の家だってバトル始まってから一度も親が家に帰ってきたことないみたいだし、いまは独り暮らしをしてるオレや浜咲だって、そんなに変わらないだろう」
「……そう思えば、そっか」
不思議そうな顔をして身長差の分で見下ろしてくる近藤の言葉に、夏姫は自分や克樹たちの境遇を思い出す。
比べてみても、灯理だけが特別酷い境遇というわけではないように思えた。
――まぁでも、アタシがあんまり口を挟むことでもないしなぁ……。
克樹のジェスチャー程度の行動は、よほど相手が乗ってこない限り間違いが起こることはないと思うし、相手が誘ってきたとしても克樹の側にはいつもリーリエがいる。
克樹自身が行動を起こさない限りは大丈夫なのだろうと思うが、夏姫は胸の中にわだかまる不安を拭えなかった。
――灯理も、可愛いもんね。
女の子の夏姫から見ても、灯理は小柄で可愛らしく、羨ましくなるほどのスタイルをしている。性格の強引さはあれども、ジェスチャー以外ではヘタレで奥手な克樹に対しては、それくらいの方が近い道なのかもしれないとも思えた。
「あんまり聞いたことなかったが、浜咲は父親はいるんだろ?」
「あ、うん。いるよ。もうずいぶん会ってないけど」
事情を話していない近藤の質問に、夏姫はできるだけの笑みを浮かべて答える。
父親とはもう一年以上会っていなかった。
再就職に失敗し、酒に溺れた父親は、自分の妻が死んだときにも、酒を飲み歩いていた。
いまは仕事をしていて、アパートの家賃と、生活費の仕送りはしてくれていた。元々の仕事とは関係ない仕事は厳しいらしく、自分でつくった借金もあって、仕送りの金額は暮らしていくことができないほど。
足りない分はどうにかアルバイトで賄うことはできていたが、余裕はほとんどなかった。
「会いたくないのか?」
「んー。あんまり。会いたくはない、かなぁ」
「……済まん」
できるだけ笑っていたはずなのに、何かに気づいたのか、近藤が謝ってくる。
それに対して目を細めて笑って見せた夏姫は、まだ早い夏の陽射しが降り注いでくる青空を仰いで、会いたいと思えない父親のことを思い出していた。
もうふたりきりの肉親なのに、父親を恋しいとは思えなかった。
生活のすべてを春歌に任せ、ひとり飲んだくれ、時には暴力を振るっていた父親だったが、彼女の死を悲しんでいないということはない。自分の行動を悔いていないわけはない。
けれど夏姫は父親を許せなかった。春歌を死に追いやった彼を、どうしても許すことができなかった。
許したいという気持ちがないわけではなかったが、まだ胸の中に残るわだかまりが、自分の父親に対してどんな言葉で話していいのか、わからなくさせていた。
「ま、みんないろんな事情があるんだよ。アタシにも、灯理にも、克樹にも、もちろん近藤にもね。だからまぁ、とりあえずはいいかな、って」
「そうか」
悔いているように顔を歪ませている近藤に笑いかけつつも、夏姫は鞄を持っていない右手で、ずきずきと痛むような胸を押さえていた。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました
フルーツパフェ
大衆娯楽
とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。
曰く、全校生徒はパンツを履くこと。
生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?
史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。



幼なじみとセックスごっこを始めて、10年がたった。
スタジオ.T
青春
幼なじみの鞠川春姫(まりかわはるひめ)は、学校内でも屈指の美少女だ。
そんな春姫と俺は、毎週水曜日にセックスごっこをする約束をしている。
ゆるいイチャラブ、そしてエッチなラブストーリー。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

GAME CHANGER 日本帝国1945からの逆襲
俊也
歴史・時代
時は1945年3月、敗色濃厚の日本軍。
今まさに沖縄に侵攻せんとする圧倒的戦力のアメリカ陸海軍を前に、日本の指導者達は若者達による航空機の自爆攻撃…特攻 で事態を打開しようとしていた。
「バカかお前ら、本当に戦争に勝つ気があるのか!?」
その男はただの学徒兵にも関わらず、平然とそう言い放ち特攻出撃を拒否した。
当初は困惑し怒り狂う日本海軍上層部であったが…!?
姉妹作「新訳 零戦戦記」共々宜しくお願い致します。
共に
第8回歴史時代小説参加しました!

【R18】俺は変身ヒーローが好きだが、なったのは同級生の女子でした。一方の俺は悪の組織に捕らえられマッドサイエンティストにされた
瀬緋 令祖灼
SF
変身ヒーロー好きの男子高校生山田大輝は、普通の学生生活を送っていたが、気が晴れない。
この町には侵略を企む悪の組織がいて、変身ヒーローがいる。
しかし、ヒーローは自分ではなく、同級生の知っている女子、小川優子だった。
しかも、悪の組織に大輝は捕まり、人質となりレッドである優子は陵辱を受けてしまう。大輝は振り切って助けようとするが、怪人に致命傷を負わされた。
救急搬送で病院に送られ命は助かったが、病院は悪の組織のアジトの偽装。
地下にある秘密研究所で大輝は改造されてマッドサイエンティストにされてしまう。
そんな時、変身ヒーローをしている彼女、小川優子がやって来てしまった。
変身ヒーローの少女とマッドサイエンティストの少年のR18小説
実験的に画像生成AIのイラストを使っています。
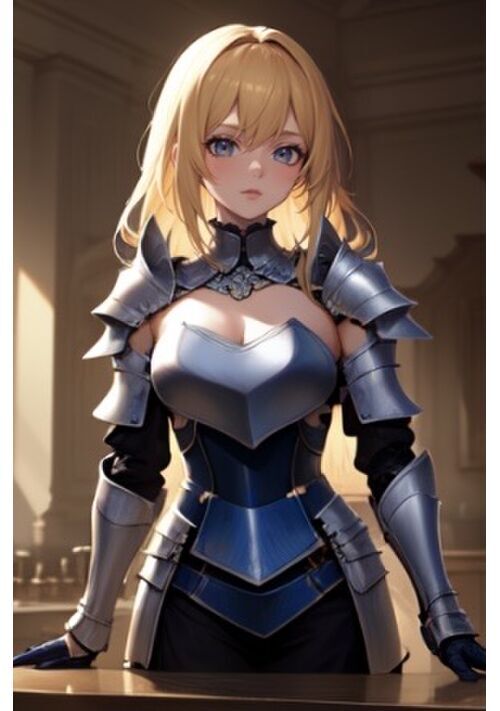
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















