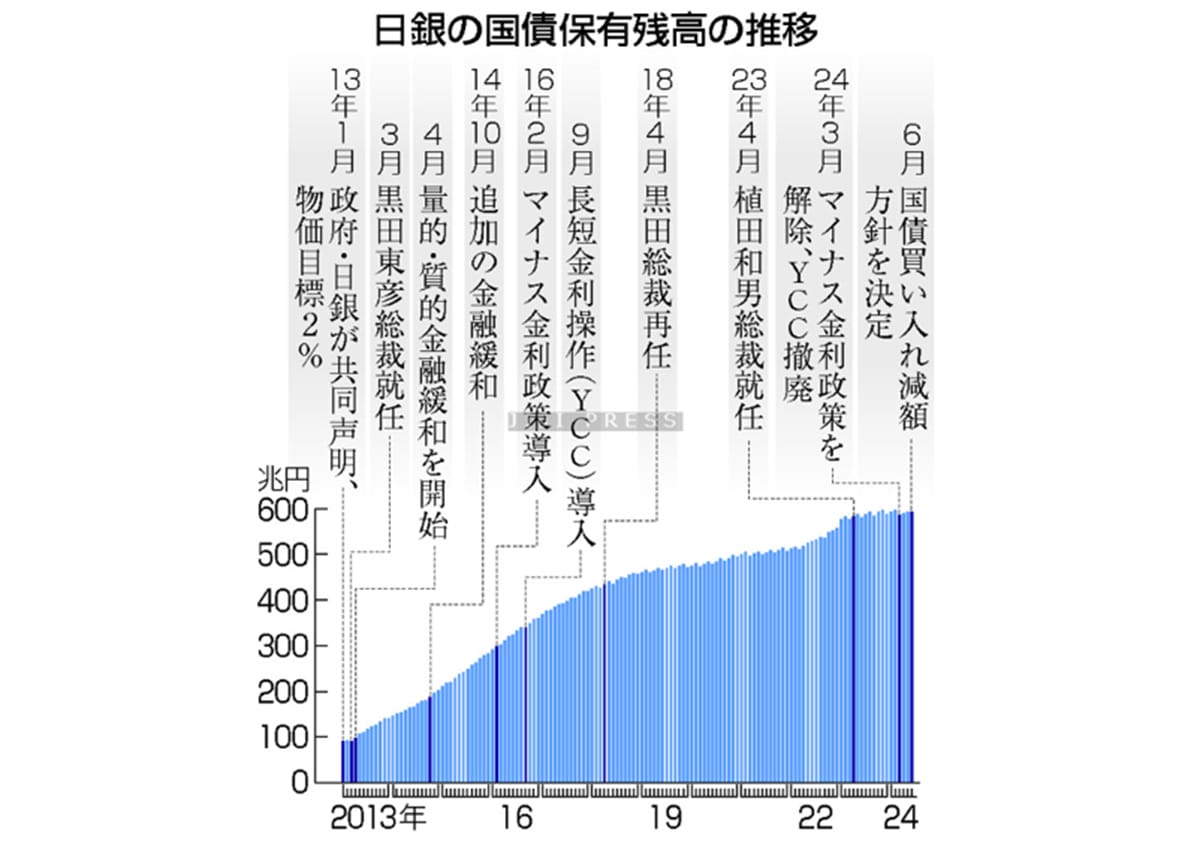
<SNS=民意なのか?>SNS選挙で「政策」は置き去りに 人類総メディア時代で大切なこと
2025.03.19
Wedge ONLINE
2024年は、日本におけるSNSと選挙の関係が大きく変化した年となった。「SNS選挙」という言葉が広まり、SNSの影響力がより明確になった。

(KYONNTRA/GETTYIMAGES)
これまで、日本の選挙ではSNS上の支持と実際の結果が必ずしも一致しないケースが多かった。例えば、東京大学の鳥海不二夫教授の分析によると、20年の東京都知事選では、X(旧Twitter)上で小池百合子氏に対する批判的な投稿が大部分を占めていたが、実際の選挙では彼女が2位候補の4倍以上の得票を獲得し、大差をつけて勝利した。
しかし、24年にはこの傾向が変化した。7月の東京都知事選では、「石丸現象」が話題となった。前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏は、ショート動画を駆使してSNS上で支持を拡大し、165万の得票数で2位に躍進。現職との票差を縮めた。
また、11月の兵庫県知事選では、パワハラ疑惑で一度失職した斎藤元彦氏が再選。マスメディアが疑惑を報じる中、斎藤氏を支援する「当選を目指さない候補者」までもが登場し、SNS上では「斎藤氏は既得権益と戦う候補」「彼を辞めさせたい勢力がいる」というナラティブが拡散され、インフルエンサーも積極的に支持を呼びかけた。ネットコミュニケーション研究所の調査によれば、斎藤氏のSNSアカウントや関連コンテンツへの注目度は他候補を圧倒しており、これが再選の大きな要因の一つと考えられる。
NHKの出口調査では、兵庫県知事選において「SNSや動画サイトを情報源とした」と答えた有権者の割合が30%に達し、テレビ(24%)や新聞(24%)を上回った。SNS時代の選挙のあり方について、今年7月までに行われる参議院選挙を前に社会全体で議論していく必要がある。
選挙は単なる勝敗ではなく
民主主義のプロセスの一つ
SNSには「可視性」、「持続性」、「拡散性」という三つの特徴がある。SNSが発達し、選挙で活用されるようになったことは、様々な世代の政治への関心を高め、民主主義の裾野を広げるという点で大きなメリットがある。実際、24年の兵庫県知事選では投票率が前回から約15ポイント上昇し、多くの有権者が選挙に参加した。
一方で、深刻な課題も浮き彫りにしている。特に「対立構図の強調」と「社会分断の加速」は看過できない問題だ。本来、選挙は政策の実現可能性を問う場であるべきだが、SNS上では「既得権益vs.変革者」「正義vs.悪」といった感情的な情報が拡散されやすく、二極化を招いている。24年の東京都知事選や兵庫県知事選でも、インフルエンサーが「敵vs.味方」というフレームを広め、議論を一層過激化させた。
このような状況が続けば、有権者は冷静な政策論議をする機会を失い、センセーショナルなメッセージに基づいて投票を決める可能性が高まる。候補者の側も、有権者の感情に訴える戦略を優先し、政策論よりも「敵を作る」ことに注力するようになる可能性がある。
選挙は民主主義のプロセスの一つに過ぎず、投票後には勝者と敗者が結果を受け止め議論を重ね、協力し合って、社会を運営する必要がある。しかし、SNSによる対立の激化は、この民主主義の一連のプロセスを妨げる。兵庫県知事選でも、選挙後に「稲村和美候補を支持した22人の市長は全員辞任すべきだ」という過激な声がSNSで広まり、社会の分断がさらに深まった。
また、SNSは極端な意見が発信されやすいというバイアスもある。SNSは能動的な言論空間であり、言いたいことのある強い思いを持った人が大量に発信することが可能で、それを止めるモデレーターもいない。中庸な意見の人は発信するインセンティブが小さいうえ、いざ発信すると極端な人に攻撃されるため、発信の萎縮も起こりやすい。その結果、「サイレントマジョリティー」の意見を埋没させている。



























